物語を書く時、「ただ面白い話を描けばいいのか」と迷うことはありませんか? 多くの読者を惹きつける小説には、著者自身の生き方や信念が無意識に息づいています。
あなたが歩んできた人生、心を動かした瞬間、そして胸の奥にある価値観――それらが物語の芯となる時、言葉は生き始めます。
この記事では、あなた自身の“世界観”を作品に活かし、読者に自然と伝わるようにする技術を紹介します。
あなたの“世界観”とは?
人は日々のくらしや仕事、人間関係の中で「自分はこうありたい」、「社会はこうあるべきだ」と感じる瞬間があります。その積み重ねはやがて信条や人生観となって、あなた独自の“思想”を形づくります。
小説でいう思想とは、難しい哲学とは違います。あなたが大切にしている生き方の指針、つまり世界と人間をどう見つめているか――その視点こそが“思想”と呼べるのです。
学問や倫理上で、理論や学説を思想の一例として挙げられますが、個人的なものの考え方も思想に属します。わたし自身も作曲家として音楽活動を長年続けてきましたので、その経験を活かして魅力を発信しようと“音楽小説”に取り組んでいます。
硬く考える必要はありません。日頃から自身で思っていることは個人で必ずあるはずです。外には発信していなくても信条として胸に秘めていることも思想に属すると考えてよいでしょう。
小説に活かせるあなたの思想・メッセージ6選
では、あなたの中にある“信念”をどう物語へ昇華させていくか。ここでは、執筆のヒントになる6つの方向性をご紹介します。各テーマは、単なる物語の題材ではなく、「読者が共感を覚え、自分の経験と重ねることができる」思想の在り方でもあります。
1.“楽しみ”
自分の中で、心から楽しいと感じていることがあるなら、ぜひ物語に取り入れましょう。例えば、料理を通して人とつながる喜び、地方の伝統工芸に込められた職人の生き様、街を歩きながら偶然の出会いを楽しむ習慣など。
「その楽しみの本質とは何か」、「なぜ惹かれるのか」を掘り下げると、単なる紹介ではない“人生哲学を持つ物語”に変わります。
仕事や趣味、ライフワークで自分で楽しく取り組んでいることで立派な素材になります。公序良俗・常識に反するものでなければどんなものでもよいでしょう。

「楽しみ」のひとつとして、わたしは時間が取れるときはなるべく、朝の散歩をするように心がけています。散歩には良い点もあり、身体の調子を整えたり、小説ネタを収集しやすい機会となっています。
また、私は日々のストレス解消のために、休みの日には日帰りで自然豊かな場所へ赴いています。そうした体験は非常に小説を書くにあたっては総合的にメリットがあります。気分転換を図ることで創作意欲も湧きますし、多くの素材を得られたり、発想のしかたが豊かになります。
こうした機会から自然と音楽と掛け合わせた紀行文的な小説『自然・音楽・こころ』を書きました。
👉例:自身で「楽しみ」と感じて小説の素材になるもの
乗馬に凝っている/“心理学”のおもしろさを広めたい/竹細工の魅力を伝えたい/休みの日には必ず知らない町に出かけてその地の名物を食べる/東海道・中山道・日光街道・奥州街道を何か月もかけて制覇した/色々なお酒を飲み比べる など
2.“激励”と“勇気づけ”
読者の心を最も動かすのは、「困難の中で希望を見出す姿」です。努力や失敗、再挑戦を描いた物語は、現実の読者に勇気を与えます。あなた自身の経験からにじみ出る“あきらめなかった瞬間”を織り込んでみると効果的です。
夢に向かって進んでいる途中で、挫折しながらも少しずつ前進を続けた主人公、孤独と向き合いながら、目的に一歩踏み出す人物――そんな描写の中に、自然と「励まし」が息づきます。
👉例:
●高等学校のサッカー部に入部し、苦しいことにも耐えながら全国大会での優勝を勝ち取ったある高校生の物語。苦労を超えた先には悦びが待っていることを表現したもの。
●極度な自閉症に苦しむ10代の男性。小学生の時に友人のいじめが原因でずっと苦しんできたが、高校卒業と同時に社会に出るのがますます怖くなり、家に閉じこもってしまった。一人だけ無二の親友がいるのだが、気にかけて何とか社交的にしようと外へ連れ出そうとする。最後は唯一その男性の好きなアニメの著者と会う機会をつくり、男性はそれを励みに勉強を続け漫画家を志す。

同じように社会復帰を望む境遇にいる方々は、上記のような物語を読むことで、自分の可能性を考えるようになります。読んだ本人にとっては勇気ある一歩を踏み出すきっかけとなる価値ある作品になりますね。
私は心がけとして、日頃から困っている人に対しては手を差し伸べるようにしてきました。“助け合いの精神”のような思想は持ち合わせていたので、この手法は使うことがあります。
公道で人がどっちに行っていいのかわからなくて困っている時、仕事上で相談に乗ってほしいと同僚に声をかけられた時、お年寄りが腰が痛そうに吊革につかまって立っている時――人々が幸せそうな顔を見ると嬉しい気持になります。そういう気持ちから人に「幸せや勇気」を与える気持ちを起こすようになりました。
3.“苦悩と喜び”の経験から生まれるもの
人は苦しみを通して成長します。小説の中では、苦悩と幸福のバランスが大切です。“生きることの奥深さ”を読者に届けることができます。
失敗が続く毎日でも、あとから意味を持つことがあります。そのような展開は心に残りやすいものです。主人公が自分の弱さを認め、新しい自分に出会う瞬間を描くことで、読者自身の希望にもつながります。
苦しい体験や失敗の中から、発見や成長、そして何よりも喜びは生まれるものと思います。今大変な苦しみと感じているのであれば、それは体験が自身の地や肉になるのです。私はそうした負担を味わった時には、ポジティブな思考を逆に持つようにしています。
それを身体で感じて、小説への発想に転換させます。主人公とその友人を介して、「人生で苦労ばかりしている人もプラス思考で生きていけば運気を上げる」ことを示唆する作品を書いています。
👉例:
●ルーズな性格で、社会的ルールに敢えて馴染もうとしないいつも食べてばかりいる20代の女性。男友達もいなく、働くのも億劫で家にいるばかり。母親に強制的にアルバイトに出されるが3日と続かない。ある時、レジ対応中の客からひと目で気に入られてしまい、本人も悪い気がせずにとうとうプライベートで食事に行くことに……。仕事中は要領を得ず、向いていないと思い込むが、恋愛のほうは順調で結婚まで発展していく。
●演劇鑑賞が好きで、大学を卒業後に放送作家をめざそうとする男性。登竜門である脚本コンクールに応募しては落選を繰り返している。ひと通りのノウハウは備えているものの、今ひとつ成果を出せないでずっと悩んでいる。プロの脚本家にも指導を受けていたが、今回で5回目の応募であったが、やはりあと一歩という講評であった。嘆き悲しむ男性は、もうあきらめようと断念しようとしたが、そこに救いの神が現れる。はたして……。
4.人間関係などからくる精神的苦痛からの解放
人間関係の摩擦は、誰もが避けられない現代的なテーマです。小説の中で、それをどう乗り越えるのかを描くことは強い共感を生みます。
社内の理不尽な圧力に悩みながら、自分の正義を貫こうとする人物。また、SNS社会で生じる誤解や孤立を通して“言葉とは何か”を問いかける物語。このような現実に寄り添った社会的テーマこそメッセージ性が高く、自然に読者に届きます。
私自身もこの人間関係には常に悩まされてきました。さまざまな経験から「救い」の想いを登場人物の行動に投映して物語に反映をしています。同じような経験がある方は、今までの経験を活かして読者へのアドバイスをしてみてください。
👉例:
●職場でパワハラ、モラハラなど、立場上の弱さに付け込む上司から逃れようと苦悩する入社間もない男性。カッとなりやすいタイプですぐに仕事上、真向から上司と対立してしまう。間もなく精神疾患に陥り、「こんなところには居られない」と辞表を突き付けて辞めてしまった。辞めたあとは、精神上も安定し試行錯誤を重ね、フリーランスで得意のWebデザインの仕事が回るようになる。
●「周囲の人間の行動が気になるタイプの人間は、接触を好まず非社交的で人間嫌いの性格である。コミュニティや人が集まる繁華街にはいくようなことはまずない。独りでいることに安心と悦びを感じる過ごし方を考えよう」と自分の思想を主張する作家。それを小説化し、それが見事に共感を呼んでベストセラーになる物語。
5.人生教訓
人生には失敗や失望は、しばしば大切な“気づき”を与えてくれます。小説で教訓を描く際は、登場人物を通して間接的に伝えるのがコツです。「努力の尊さ」、「欲のもろさ」、「誠実さの大切さ」などが読後に自然と残るように仕立てましょう。説教でなく“鑑賞の余韻”として読者の心に残ります。
👉例:
●将来、政治家を志そうとする決断力のある男。自分の不利益になることは一切関心を示さない。おまけに利権の絡むことばかりに介入するが、メリットになるようなことにはつながらない。「損して得取れ」の精神を知らずして、「いいとこ取り」の性格が招く不運な境遇を表現。
●一つひとつの物事にすべて深い意味があることを認識せずに、浅はかな思考しかできない人物の物語。思考力のなさに、友人や職場では呆れられてしまう始末。最後は奥行きのある社会構造に打ちのめされ、友情や職を失う結果となり、後になって洞察力のなさを痛感する。
二番目の例は、特にわたし自身の思想観に対する想いを挙げてみました。何もそのことの意味を理解をせずに人や物事に安易に悪評をくだすことは避けるべきだとの思いから発想したものになります。

“教訓を学べる小説”は誰にでも幅広い層で読めて、ターゲットが広くなるのでおすすめです。
6.倫理的警告
社会生活の何事も、マナーを守ることによって一定の秩序が保たれています。なかには一部の好き勝手な行動によって規律が乱れ、ルールから逸脱された状況が見られることもあります。
そのようなマナーの守れない哀しい現実を描き、マナーの向上を訴えかける作品も共感を呼びます。
例:短編として
●歩きながら物を食べては、ごみをポイポイ捨てる近隣の高校生をいつも目の当たりにしている住人。マナーの悪さをいつも気にかけていた。ある日、集団で歩いていた高校生の一人が、飲み終わったペットボトルをそのまま道になげ捨てたので注意したら、「ちゃんちゃらおかしいぜ」とにやけ顔で去って行った。信号も無視して横断歩道を渡っていたが、その直後、ゴミを捨てた少年だけがトラックに巻き込まれて即死した。
●自分の主張ばかりを優先して、店で大声を出して苦情を言い、周囲に迷惑をかける女性。店員が謝罪しているところへ、その一瞬、いきなり強盗が入口から侵入し、拳銃を発泡したが、運悪くその女性客の足に命中し、救急車で病院に運ばれてしまう運命に……。強盗は何も盗らずにすぐに逃げ、その場にいた店員と客は無事だった。
「伝える」より「滲ませる」創作術5選
“思想を伝えること”は、声高に訴えることではありません。むしろ、物語の奥に静かに流れる思いを感じさせることが重要です。
登場人物の行動、ストーリーの構造、場面の描写、モチーフの使い方など――創作要素の中に自然と思想を滲ませることが、説教臭さのない表現に仕上がります。
そこで、読者に「伝わる」のではなく読者が「感じ取れる」ための5つの方法を紹介します。
1.思想を「物語の構造」に埋め込む
直接、思想を語りかけるよりも効果的に読者を惹きつけるには、物語の構造に反映させる方法があります。例えば、「人間は自由に生きることができる」という思想を描きたい場合、登場人物が束縛から解放される物語にするといいですし、あるいは、自由を追い求める過程を描き、最期は破滅してしまう物語にすることもできます。
ポイントとしては、
カミュの『異邦人』は、ムルソーの無関心という生き方が、彼の行動と裁判の過程そのものによって「不条理」という思想を浮かび上がらせているのが特徴です。著者が声高に「不条理とは〜で」と説くのではなく、構造全体が思想で表現されています。
自分の思想をまず「観念」で表現せずに、「構造の動き」にはめ込むのが秘訣です。
2.思想を「人物の選択」に託す
登場人物は、思想を最も生々しく映し出すことができる著者の分身的存在です。ただ、単にそのまま露骨に語らせると説得力を失うかもしれません。
むしろ、異なる立場の人物たちが思想をぶつけ合うほうが、より読者は深い理解を示します。
ここでは、トルストイの『アンナ・カレーニナ』を挙げましょう。アンナの情熱とリョーヴィンの理想主義が対照的に描かれ、それぞれの行動が「幸福とは何か」という作者の思想を立体的に浮かび上がらせます。思想を一人だけに浴びせずに、複数の人物に分散させると、物語全体が呼吸を始め、まとまりやすくなります。
自分の考えに反する人物も登場させ、その人物にも誠実な動機を与えましょう。読者は「思想を押しつけられる」のではなく、「思想に接して揺さぶられる」体験を得ることができます。
3.思想を「描写の視点」に滲ませる
思想は真の言葉だけでなく、描写の仕方にも現れます。同じ風景を描いても、比喩の使い方や焦点の当て方で、作者の世界観はより明確性が出ます。
例:
●「夕焼けが美しい」と書く代わりに、「街が血のように染まっていた」と描けば、著者の心理やその世界をどう観察しているのかが伝わります。
●夏目漱石の『こころ』の先生の叙述の重苦しさ、太宰治の『人間失格』の断罪的な語り口、これらは思想が「視点」として滲み出ています。
自分の思想を言葉で説かずに、風景や状況で「世界をどう捉えて見ているか」を描く方法です。それだけで、小説全体が思想の反映体に見えてきます。
4.思想を「象徴とモチーフ」に託す
思想を象徴的なモチーフの形にして、繰り返し登場させる方法です。
自分が「人間の孤独」についての思想を持っているならば、例えば、一匹の鳥の行動をモチーフとして託してみる。また、「現代社会の喧騒」に対する違和感を感じるならば、無音の空間に存在する壊れた時計を象徴として機能させてみるようなイメージです。
“モチーフ”を使って、思想を直接語らずに表現すれば、読者の感覚に届かせることができます。また、“繰り返されるイメージ”にも、無意識に読者の中で思想を形づくらせる力があります。物語を読む体験が「思想との対話」をつくることができるのです。
例:
●カフカの『変身』の「虫」、ヘミングウェイの『老人と海』の「海」、これらは単なる設定ではなく、作者の人生観を象徴している偉大な作品です。
5.思想を「語らず」して残すテクニック
小説は理論書でも宣言文でもありませんので。読者に想像させ、“感じさせる余白を残す“特徴を有しています。「語らない部分を残す」を意識し、物語の展開で信条・価値観を読み取れる作品は深く生き続けます。
例:
●村上春樹の『ノルウェイの森』では、青春の死と喪失が中心にありますが、作者はその「意味」を一切説明はしていません。読者は登場人物たちの沈黙や時間の経過の中に、著者の人生観を読み取ります。つまり、思想とは、語り尽くさないことで完成するのです。
自分の思想を物語の中で“提示”するのではなく、“漂わせる”テクニックの取得に努めましょう。その余白にこそ、読者が自分の思想を見いだす余地が生まれます。
あなたの “思想観” を育む習慣
「思想を物語に埋め込む」と言っても、初心の方にが行動に移すことはなかなかむずかしいものです。小説を書くうえで、日頃からメッセージ性の高い作品を書くにはどのようなことを心がけていればよいのでしょうか。そこで、誰でも取り組めるアクションの一例をここではご紹介します。
まず読書の習慣を持ちましょう。小説だけでなく関心のある分野の入門書、専門書もおすすめです。読書以外であれば、SNSやインターネット上でその分野の専門家のページなども利用して深読みしましょう。いずれも繰り返熟読することが大切です。
読書だけではなく、生活や仕事・目に留まったり、気になることで、面白く感じたり、違和感のあることも探してみてください。
大事なことはメモやスマホアプリに書き留めておきます。この作業がないと、時間が経つにつれて忘れやすくなります。
書き留めた内容について、自分はどう思うのかを考える時間を持ちます。善悪の観点からの自分の判断や考え方を十分に深めましょう。
自分なりの考えた結論を出す習慣をつけるようにします。思考を重ねた考え方は自然と頭と身体に沁み込みしっかりとインプットされていくでしょう。口頭で主張できるくらいまで、何度も思考をめぐらせてみると、それが思想として形成されることになります。
上記の習慣を続けていると、自分の日頃考えている信念・思想を持つことができます。思想や物の考え方を小説に反映できることでしょう。
上記のステップは参考です。日頃から、物事の判断、思考を重ねる習慣があって、思想感を持っている方は即、執筆に活かしましょう。
まとめ:思想を「読ませる」よりも「感じさせる」こと
小説は、言葉で思想を語るのではなく、登場人物や風景、沈黙の中にそれを“匂わせる”芸術です。あなたの信念が物語の呼吸として息づくとき、読者は「これは自分の物語かもしれない」と感じます。
露骨に読者に語り、思想を読ませるのではなく、感じさせる――それが、長く読み継がれる作品の根となるのです。
思想をうまく反映させるとは、つまり「思想を滲ませること」。そのために必要なのは、語りすぎず、構造や描写に信頼を置く姿勢です。
物語の奥に流れる信念は、読者の心に作品の「思想」として長く残ります。主張することではなく世界観として、言葉ではなく物語全体から伝わること。自分の思想を小説に託すとは、そうした静かな表現の技を磨くことが大切と言えるでしょう。
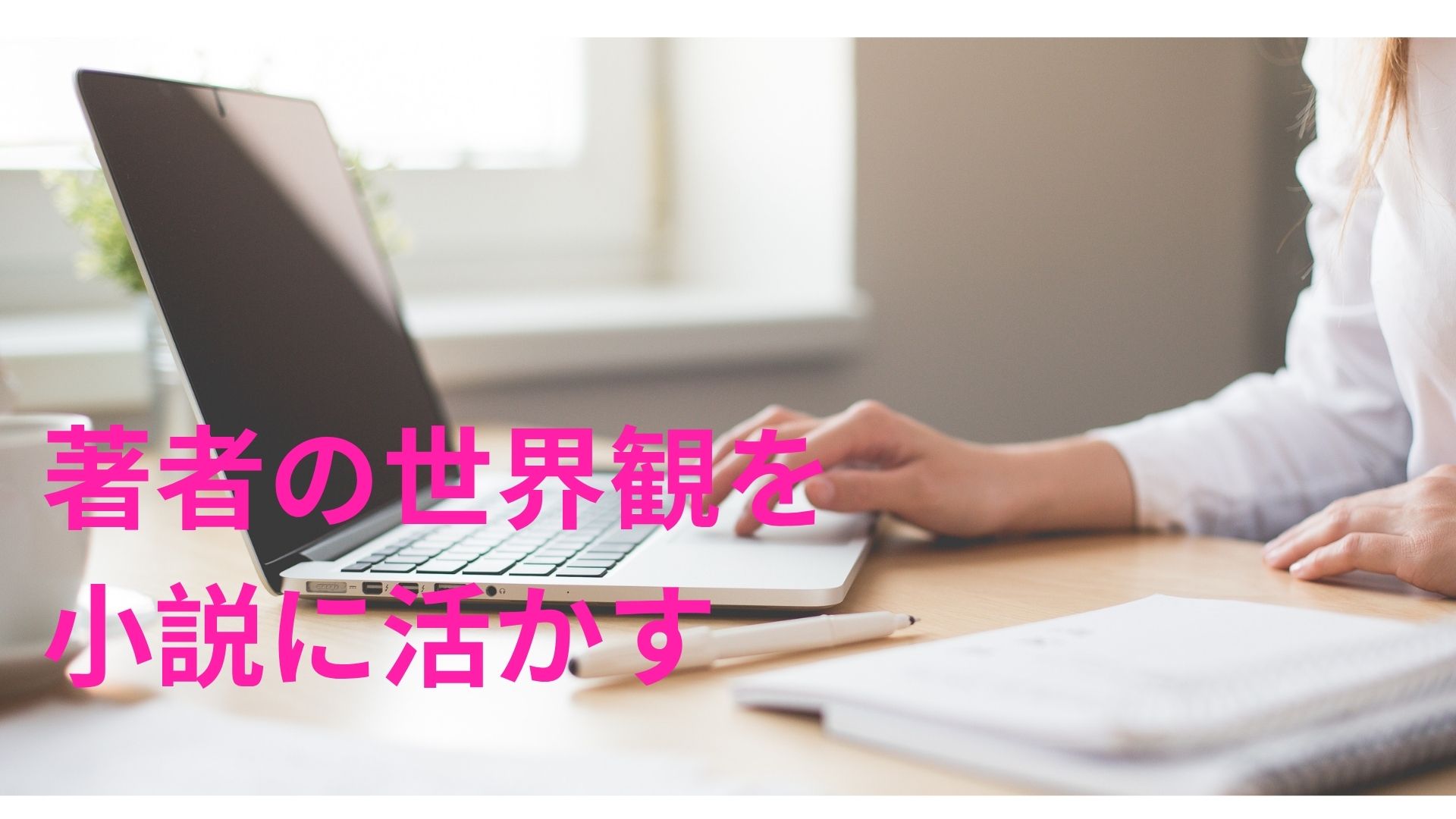


コメント