小説において、冒頭の数行、あるいは最初の一文ほど、作家の力量と感性が問われる部分はありません。読者がその物語の先を読み進めるか否かは、この一文に仕掛けるテクニックにかかっていると言っても過言ではないのです。書き出しで悩むケースは誰でも経験することですし、プロでも一度でスラリと書けることは多くないでしょう。
この問題は小説家がこれからも悩み続ける問題ですが、私もようやくいくつかのテクニックを心得ることができました。ここでは、「書き出しで覚えておきたい留意点」と「読者の心を捉える創意工夫点」を自身の経験側からお伝えします。
「書き出し」で覚えておきたい留意点6点
多くの小説指南書は書き出しが読者を引き込むうえで重要だと説いています。読者が初めの一文で、その小説が面白いかどうかを判断することが多いからです。書き出しを一度で完璧に書ける作家は少なく、誰もが何度も推敲を重ねています。
1.多くの作品を読み、書き出しの奥義を知ろう
私自身が小説を書き始めたころは、出だしの文を考えてもなかなか浮かばなかったので、「どこから書き始めてよいのか」と何日も悩み続けました。特に印象に残っているのは、村上春樹さんの作品を読んだ直後、自分もあの語り口調を真似してみようとしたものの、納得のいく一文が書けず、下書きのノートを何ページを無駄にした経験です。
そのとき、「自分なりの書き出し」を見つけるために、毎朝10分の時間を取って、好きな作家の冒頭文を音読し、感じたことをメモをする習慣をつけたのです。これを続けているうちに、少しずつ自分のリズムや言葉の選び方に変化が生じてきたのを実感しました。
多くの作品に触れて、良質の書き出し文を書ける感覚をつかんでください。
2.最も重要でインパクトのあることばを早い段階で用いる
小説ではありませんが、次の評論を引用してみます。
「この「芸術新潮」に、フルトヴェングラーの文章が連載されていたが、その中にひどく心を摶たれた一行がある。」
三島由紀夫『楽屋で書かれた演劇論』
冒頭の一文ですが、その先を読んでみたくなる名文です。このように、次の文へと誘うテクニックは最も効果的な手法のひとつになります。私も先に結論を言って、「じゃあ、それはいったいなぜ?」と思わせる手法は過去に使用したことがあります。
3.短く、少ない簡潔な表現で多くを語る
私が初めて文学賞に応募した短編小説では、冒頭の状況を長々と説明してしまい、審査講評では「最初の一文で世界観が伝わらない」と残念な指摘がありました。それ以来、一文でどれだけ読者の関心を引けるかを意識するようになっています。
たとえば、実際に「雨音だけが部屋を満たしていた」という一文で始まる作品でこの一文だけを友人に見てもらったとき、感想として「この続きは読んでみたいね」と言われた経験があります。このように、自分の体験からも、短く印象的な一文にする大切さを身に染みて学びました。
「恥の多い生涯を送ってきました。」
太宰治『人間失格』
「吾輩は猫である。名前はまだない。」
夏目漱石『吾輩は猫である』
上記の二例は特に有名で、大変広く親しまれている作品なのはおわかりでしょう。短く語ることによって、読者の想像をかき立てることが重要なのです。
この太宰治の一文は読者に「えっ、どんな生涯を送ってきたの?」と思わせる、先へと導く力を備えた書き出しです。漱石は簡潔な書き出しで猫自身に語らせ、この先に何が起きるのか期待しないではいられません。

無駄な言葉を削ぎ落とし、読者に与える第一印象を大切にすることが作家の心得のひとつです。
4.形容詞の修飾を重ねすぎるのは禁物、効果は低減
形容詞の使い過ぎには注意が必要です。描写における多重の形容は読者の想像力を逆に阻害してしまいます。形容詞は文章の骨格に装飾をしていくものですので、表現したいことが逆にぶれやすくなります。使っても一つのセンテンスで適切な形容詞一つだけにしましょう。
👉例1:その男、不気味で恐ろしい目つきをしている。➡︎ その男、恐ろしい目つきをしている。
👉例2:その淡いピンクの口紅はきつい匂いのするものだった。彼女は使用することにいつも悩んでいた。➡︎ その淡い口紅は匂いがきつく、彼女は使用することにいつも悩んでいた。
例1では恐怖感が鮮明に文章に現れますが、読者がどう想像するかを考えていないことになります。読者が想像できる余地が必要であることを念頭に置いておきましょう。
例2ですが、最初の句読点までで、文章の構成のまずさが挙げられます。一度「淡い」と装飾した口紅を、また後半で「きつい匂い」がすると、再び口紅を修飾しています。この文章を形容詞で修飾している部分を一つにして後半を副詞として動詞を修飾し、その口紅の使用について考えていたという一文にするとスッキリとしてきます。
書き出しで読者の想像を膨らませる考え方と同様です。その人を想起するに相応しい特徴のみを挙げておけば、読者の想像力は次第に拡大し、独自の人物像を形成していきます。そうであれば、読者はもうその物語の展開に乗り始めたと言っても過言ではありません。
5.結末を匂わせる導入や緊張感を漂わせる工夫
意味深なひと言で物語の全貌や結末の想像がつくきっかけを得ると、そこから読者は関心を持ち始め全体像を探ろうとします。有名な例を挙げますが、このフレーズが冒頭で語られ、物語全体のトーンや結末の真相を暗示しています。
「この世には不思議なことなど何もないのだよ」
京極夏彦『姑獲鳥の夏』
「蒲田の操車場で、死体が発見された。」
松本清張『砂の器』
事件の発端が、物語の結末で明かされる真相へとつながる構成です。どちらも冒頭で物語の核心や結末をほのめかす印象的な書き出しです。
私の短編『郷愁』は、最初の一文に「この手紙が届くころには、もう私はここにはいないだろう」という出だしで始まります。ある読者からは「初めで、一気に引き込まれた」とレヴューをいただきました。自分の経験からも、冒頭で結末を想像させる表現を一部入れることで、読者の関心を強く引き付けられるものと実感しています。
また、初めから緊張感のある書き出しで始めても効果があります。
「昭和二十年八月六日の朝もやの中に、広島市の空をB29型爆撃機が一機、東から西へ低空で飛んでいた。」
井伏鱒二『黒い雨』
この一文からは緊迫した不安感を読者に抱かせます。ただならぬ空気が伝わり、戦時中の緊張と不穏さが、読者に直ちに迫ってくる印象的な書き出しです。
「男がいなくなったのは、八月の終りである。」
阿部公房『砂の女』
短く簡潔ながら、何かが起こったという不穏な空気を感じさせます。「いなくなった」という曖昧な言い回しが、読者に想像を促し、自然とページをめくりたくなる導入です。
どちらも、静かな語り口の中に潜む異常性や緊張感が日本文学ならではの技法で表現されています。文章の空気感や時代背景に注目して読むと、より深く味わえる作品です。
6.登場人物の輪郭をぼんやりと
登場人物の紹介を冒頭にすべきか否かもまったく様々です。少なくとも、物語を牽引する存在の「気配」は示しておいたほうがよいでしょう。人物が最初から登場しない場合でも、その視点や存在感がにじみ出ていれば、読者は物語の「誰に注目すればいいか」を理解することになります。
ここで重要なのは、「こまごまと説明しすぎない」という点です。登場人物の身体的特徴を並べたてるのは逆効果で、読者を引きつける素材にはなりません。読者にすべてを与えるのではなく、「知りたい」欲求をかき立てる余白を残しておきましょう。そのためには、「曖昧さを恐れない書き方を意識するテクニック」を身に付けてください。
「僕は三十七歳で、そのときボーイング747のシートにすわっていた。」
村上春樹『ノルウェイの森』
まさに第一行目で、回想形式の導入です。具体的な情景よりも「心の状態」や「気配」が重視され、主人公の人物像をじわじわと浮かび上がらせるような一文です。
繰り返しますが、登場人物の説明を地の文で細かくして、読者に状況を理解してもらうのは得策ではありません。かえって面白みを感じないものにしてしまいますので、「人物をこと細かく描写に努める意識」は捨てましょう。
文章の簡潔さ、ふんわりとした人物の描写、先を暗示するキーワードの設定などは、書き出しのコツとして、毎日の執筆の継続でわかるようになります。私の場合は書き終えて、その後の推敲の段階で、身に染みて理解できるようになりました。今すぐに意識できなくても、執筆の継続を通して潜在的に得られるでしょう。
魅力的な小説の書き出しに求められる、読者の心を捉える創意工夫7選
物語の構造と性格、文体、読者の心理、文化的背景など多角的な視点から、魅力ある書き出しを創り出すために工夫すると良い点をお伝えします。
1. 書き出しは「物語のとびら」を開ける役割がある
書き出しは、物語の世界への入口になります。読者は現実から切り離れて、未知の世界へと足を踏み入れるのです。その導線として、「世界観の提示」、「語り手のトーン」、「物語の焦点の提示」の三点の機能が同時に求められてきます。
👉例:「午前0時、東京の空は灰色に沈んでいた」
上記の書き出しは、時間と場所、そして何らかの陰鬱な気配を伝えます。冒頭の一文で読者の五感や想像力を刺激する機能があり、併せて上記の三つのポイントをカバーし、物語への没入を促します。
「青豆は、タクシーが高速道路の非常駐車帯に入ると、まず耳のピアスをはずした。」
村上春樹『1Q84』
普通の現代都市と思わせておき、「非常駐車帯にタクシーが入る」という非日常感から、これから何か異質な出来事が起こる世界観を醸し出しています。淡々とした描写ながらも、微妙に緊張感が漂い、村上春樹特有の静かな語り口が生きています。「青豆」というキャラクターにいきなりスポットを当てて、行動や内面に物語がフォーカスされることが明示されます。
「ある日の暮方の事である。一人の下人が、羅生門の下で雨やみを待っていた。」
芥川龍之介『羅生門』
世界観の提示:荒廃した平安末期の京都という、閉塞感のある時代背景が即座に伝わり、やや客観的で冷静な語り口から、文学的で理知的な印象が生まれます。下人という一個人に視点を集中し、その後の「善悪の葛藤」という核心に向かっていく足がかりが示されています。

物語の冒頭では、どのような世界なのか、語り手の性格や視点を明確に示すことが大切です。
2. 時間と空間をつかむ
私は書き出しには、読者が「いま、どこにいるのか」「いつの話なのか」という基本的な枠組みを自然に理解できる情報を組み込むようにしています。特に時間の設定は物語全体に大きな影響を与えるものです。古代、未来、現代、非現実的な時制など、それぞれが読者に異なる期待を抱かせるエッセンスになるのです。
空間の描写についても同様で、漠然とした描写よりは、読者が具体的に想像できるような鮮明なイメージを置くことが重要です。例えば「軋む床板の上に広がる、埃をかぶったピアノ」が登場すれば、それだけで読者は古びた空間に身を置くことになります。
山路を登りながら、こう考えた。
智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。夏目漱石『草枕』
「山路を登る」という空間的な行動が、自然の中を進む情景を読者に想起させています。自然に囲まれたなかで思索へと入り込み、思考的内面と外界(自然)との接点を描く構図を狙ったものです。「山路」という空間を思索にふける舞台とする設定で、日本文学における自然と心象風景の結びつきを象徴しています。
私は時空間的な描写をよく用います。『アーティスティックカタルシス』という作品では、異次元ツアーの誘いにこんなひと言を付しています。
「あっ、この書を眺めているそこのあなた、一緒にこの画に飛び込んでみません? 不思議な体験と新たな発見ができるかもしれませんよ。(後略)……」
3. 驚きや違和感というカギを使う
読者の目を引くためには、日常にはない要素、あるいは違和感を誘う要素を意図的に盛り込むのも一つの手になります。
👉例:村上春樹『羊男』、『耳をなめる女』
現実には存在しない人間、状況が不意に登場するのですが、それが読者の注意を一気に惹きつけます。
ただし、あまりに唐突すぎると読者を困惑させてしまうことになります。そのため、違和感と整合性のバランスが求められくることに注意が必要です。奇抜であって、当然、物語の本筋に深く関わっている必要があります。
「春が二階から落ちてきた。」
伊坂幸太郎『重力ピエロ』
季節が「落ちてくる」という非日常の世界観を、思わず自問させる軽快で捻らせる導入です 。
「桜の樹の下には屍体が埋まっている。」
梶井基次郎『桜の樹の下には』
「桜」と「屍体」のギャップが強烈な印象をもたらしています。恐怖や無常観の象徴と美しさが並ぶ、日本文学史に残る衝撃的な一行になります。
「3回うがいをしてから持ってるガムを噛め」
4. 文体とリズムの選定
書き出しだけに限る問題ではありませんが、文体は、単なる文章の形式ではなく、作家の視点や感性がスタイルとして表出します。書き出しには、作者の「声」が反映されので、同じ内容でも文体が異なれば印象は大きく変わります。
短文でテンポよく進めるスタイルは読者を素早く引き込む効果があり、一方で長文でじっくりと状況や心情を描くスタイルは、静けさや重みを持たせることができます。いずれにせよ、冒頭では「この物語にはこの声がふさわしい」という適切な判断のもとに文体を決めるようにしましょう。
「申し上げます。申し上げます。旦那さま。あの人は、酷い。酷い。はい。厭な奴です。悪い人です。ああ。我慢ならない。生かして置けねえ。」
大宰治『駆け込み訴え』
「箱をあけると、その中に、また小さい箱があって、その小さい箱をあけると、またその中に、もっと小さい箱があって、そいつをあけると、また、また、小さい箱があって、その小さい箱をあけると、また箱があって、そうして、七つも、八つも、あけていって、とうとうおしまいに、さいころくらいの小さい箱が出て来て、そいつをそっとあけてみて、何もない、からっぽ、あの感じ、少し近い。」大宰治『女生徒』

最近は文体の工夫のしかたで笑いを誘ったり、ユニークな語り口の作品に仕上げることを考えるようになりました。作品の特徴を出すには最適な方法だと感じています。実践ではとても効果的な手法ですのでお勧めです。
5. ジャンルと読者層の意識
書き出しに含める要素は、物語のジャンルや想定される読者層によっても大きく変わります。
ミステリーであれば謎や異変の兆候を示すこと、恋愛小説であれば感情の揺れや関係性の輪郭を早い段階で匂わせるのが効果的です。また、読者層の年齢や背景を考慮すると、言葉の選び方や構文の難易度も変わってきます。
自身の書く作風から、読者層をあらかじめ限定することもあるかと思います。私はティーンズにはティーンズ向けの直感的で視覚的な書き出し、シニアにはシニア向けの深読みできる文脈で楽しめるように工夫をしています。それぞれの対象の世代にフィットした書き出しを生み出すようにしましょう。
6. 日本語特有の美意識と間
私は書道を少し学んでいたのですが、小説の書き出しにも「余白」や「間」に感じる美を摘要する意識を持つようになりました。たとえば登場人物が黙って窓の外を見つめる描写を入れれば、読者がその心情を想像できる「余地」を残すことができると気づきました。書道と同じく、言葉を詰め込みすぎないことで、物語に深みや余韻が生まれると実感しています。
この「余韻」と「間」を意識した文章構成を心がけると、とてもおもしろくなります。俳句などに見られる季語やことわざを文中に潜り込ませ、自然描写を通じて心情を示すのです。私の『B&M』という作品では、ことわざを使用して心の豊かさを表現してみました。風情に感情を重ねる表現は、日本語の特性を活かした書き出しと言えます。これは単に美しいだけでなく、読者の感性に訴える強い力を持つものです。
「〝ふるさとは遠きにありて思うもの〟。自宅を故郷に見立て、居慣れた場所でストレスフリーに過ごすのは心が満たされものだ。」
7. 結末への布石としてのキーワードの使用
優れた小説の多くは、書き出しにその物語の「キーワード」を秘めています。最初は意味のないように見えた描写でも、終盤で驚くべき意味を持ち始めるという構造は、読者に強い印象を残すもの。書き出しに何気なく置いた言葉が、最後に大きな意味を持つよう構成されている作品は、読者の記憶に深く刻まれることになります。
そのため、書き出しにはある種の「種」を埋め込む意識が必要です。たとえ読者が最初は気づかなくとも、後にその「意味」に気づいたときの快感は、文学の醍醐味にのひとつとなるでしょう。
生卵を割ったら黄身が二つ。早朝の台所で朝ごはんの支度に余念なく、スクランブルエッグを作るみごとな手さばき。
まとめ
書き出しはその小説の「顔」であって、同時に「魂の核」でもあります。その示された一行が、物語全体を支えるための骨格となっていると言っても過言ではありません。
魅力的な書き出しを書くためには、技術と感性、計算と偶然、理論と直感の融合が求められます。読者に物語を「読ませる」のではなく、「読まずにはいられない」と思わせる一文を生み出すことこそが、作家として冥利につきることなのではないでしょうか。
はじめから納得のいく一文を書くというのは難しい話です。それは日々の訓練から得られるものと三嶋由紀夫氏も述べています。焦る必要はありません。私自身も書いて文章の心得のひとつひとつを少しずつ身に付けてきましたので、書く習慣を維持していくことは非常に大切だと思っています。
書き出しの一文をひねり出すには上記に示したようなさまざまなテクニックがあります。自身にフィットした方法で、独自性を匂わせた個性ある作品を書いてみてください。
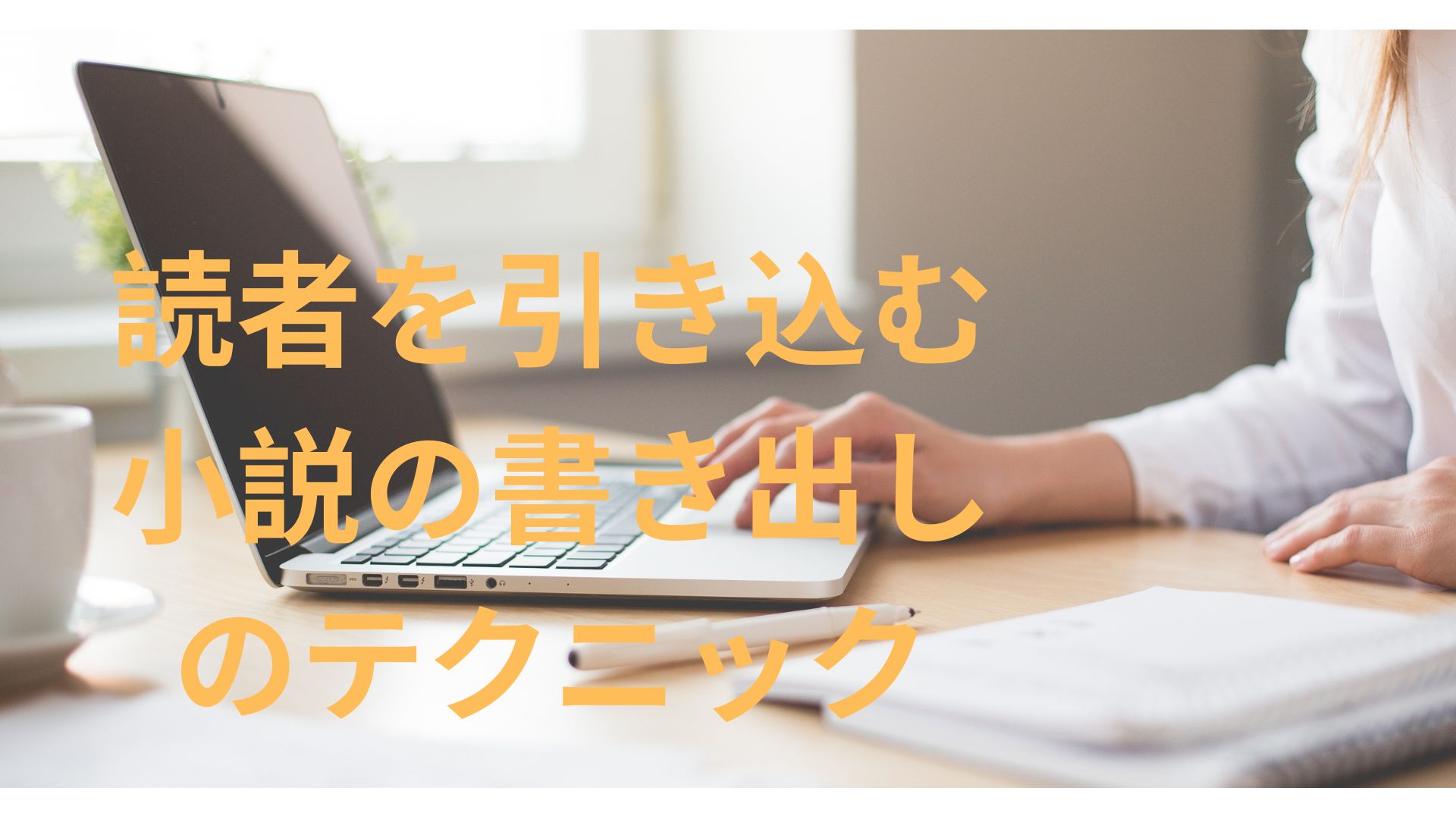


コメント