「自分には特別な才能もドラマもない」、「人並の人生では面白い物語は生まれない」と感じたことはありませんか? でも実は、誰もが過ごす日常や小さな悩み・喜びにこそ小説の材料があり、個性のある物語の源泉となるのです。
この記事では、生活・仕事・悩み・趣味などの実体験からオリジナルな小説ネタを発掘し、読者に深い共感が生まれる方法を、一次情報を交えて詳しく解説します。
本記事のポイントとして、私自身のリアルなエピソードや失敗談を増載し、皆さんが自分なりの物語づくりに活用できるワークやQ&Aを充実させています。
知識や経験のストック
小説の素材は決して ”非日常” の世界だけに留まるものではありません。私自身、親から独立して独り暮らしを始めた際に感じた世間からの疎外感、図書館で偶然にも出会った一冊の本が人生の転機になった体験、部活動で味わった悔しさなど、日常の断片を事あるごとにメモ程度ですが記録してきました。そして、それらを物語の背景に活かしてきたのです。
特に「家族間の小さな価値観の違い」は後の人生の方向性に大きく影響しましたし、「就職活動で企業から受けた意外なひと言」がきっかけで、自分の時間を大切にする意識を持てるようにもなりました。
このような経験は誰にも書けない細やかな心理を描いて小説に活かすことができるのです。
お勧めは、思い出したその瞬間にスマートフォンのメモアプリ、紙のノート、ボイスレコーダーなど使いやすい方法で「体験・背景・感情」の3点を記録しておくことです。
1.生活環境から書く
たとえば、あなたが朝通勤する途中で見かける商店街の様子、毎週末に通っていた公園での小さな出会い、家族にだけ伝わる独自の言い回し――こうした「自分しか知らない生活のカケラ」は、誰とも重複しない物語の核になる材料です。
私の小学生時代に祖父母宅で買われていた犬の「足のクセ」や、夏休みの朝に聞こえてくる爽やかなラジオ体操の音楽を物語の冒頭で使い、読者から「昔の懐かしい様子を思い出した」というメッセージをいただいたことがありました。
また、集合住宅での生活や両親の共働きで感じていた孤独感を、そのままキャラクターの設定で織り込んで、読者の共感を誘うコメントを多くもらいました。ポイントは「地味でも事実にこだわる自分独自の目線と価値観」を再発見することです。
他の記事と違う点を意識し、些細な音、景色、ふとした瞬間の「自分にしか気づかない感情」を積極的に描写しましょう。
👉例1:
●志賀直哉『城の崎にて』
実際に体験した事故後の療養生活や心境を、感情豊かに作品化したものです。城崎温泉での療養生活を題材に、洗練された文章で描かれています。
●大宰治『人間失格』『津軽』
自身の内面的な感情や育った環境の投影、また青森の故郷への想いが濃厚に表現されています。『津軽』は青森の津軽地方を旅した体験をもとに、紀行文学風に描かれた作品です。

「特に何もない」という方も “日常の積み重ね” で何かが見つかるはずです。通勤電車で見た光景、家族との小さな言い争い、商店街の店主の口癖――いろいろと考えられます。これらも丁寧に拾えば、物語の背景を彩る素材です。
2.職業上の経験を書く
職場で誰にも共感されにくい「孤独」や「理不尽」を感じたことはありませんか? わたしが飲食店のアルバイト時代に体験した「新人教育の不安」と「常連客からの激励のひと言」は、そのまま短編小説のモチーフになりました。
仕事を通じて遭遇する課題や人間関係の「裏話」こそが、独自のエピソードになるのです。実際に仕事中に感じたちょっとした失敗への感情、苦い思い出、思いがけない成功への喜び……すべてが物語の深みを生み出す要素です。細かな職場でしか使わない独自用語、現場の空気も採用してみましょう。
「どんな時にやりがいや達成感を覚えたか」、「困難をどう乗り切ったか」を振り返り、自分なりの体験から悩む成長ポイント、このような裏話を豊富に書き加えましょう。「同業者にしかわからない悩み」にも多くの人は共感します。
👉例2:
●白石一文『君がいないと小説は書けない』
出版社勤務をされていた編集者としての経験、作家としての周囲の人間関係や家族との関わりなど、自身の体験が題材になっている興味深い作品です。「私小説風」の側面を持ち、タイトルからも一度は読んでみたいと思わせる作品です。
3.自分の関心事から書く
私の長年の魚釣り・野球観戦・写真撮影――これらの趣味も、物語のネタとして色濃く使ってきました。たとえば、釣りで初めて失敗した深夜のエピソード、球場で偶然隣り合わせた熱烈ファンとの盛り上がったやり取り――こうした ”趣味を通じた人間関係のひとコマ” にリアリティが生れます。
自分が情熱を傾けているものであれば、読者の専門知識に頼らずに、細かなディティールやその世界だけの言葉づかいを採用してみましょう。「釣果ゼロの日の悔しさ」も「勝利の瞬間の高揚感」も、個性的なストーリーの一部として映えることでしょう。
”趣味ならではの専門用語” 、”仲間との価値観の違い”、“屈辱のエピソード”を積極的に挿入し、そこから主人公や登場人物の友情などにリアルな厚みを加えましょう。自分が情熱を持てるジャンルは必ず説得力につながります。
👉例3:
●夏目漱石『吾輩は猫である』
漱石はとても猫好きとして知られています。身近にいた猫を題材にして、猫の立場で人間の社会をアイロニー風にユーモアを交えて描かれた作品です。漱石自身の関心として、日常の観察眼が鋭く盛り込まれていることがわかります。
● 宮沢賢治『銀河鉄道の夜』
賢治は天文学や鉄道に強い関心がありました。星座や天体観測が趣味の一部として、その知見の深さが効果的に反映されています。星々の名前や天文学的な知識が物語中にあふれ、幻想的な世界観に包まれた夢の膨らむ作品です。
4.人生で経験した事を書く
人生における印象的な出来事ほど、小説のリアルな ”核” になります。私は若い頃に一人で初めて海外に旅行して感じた孤独、文化の違いにホテルで困惑した夜を下敷きに物語を書きました。また、祖父を亡くしたときの喪失感や家族とのささやかな再会のエピソードなど、心を大きく動かされた体験はどんなジャンルでも、作品に深い印象をもたらします。
日記やエッセイ的な短い文章からでも始めてみましょう。リアリティがにじみ出る小説は結果的に多くの人の共感を呼ぶはずです。
👉例4:
●芥川龍之介『トロッコ』
芥川が幼少期に現実として体験した、「トロッコに乗った心に残る冒険」が動機になっています。一時の興奮と楽しさがその後に取り残される恐怖に怯え、戦慄に襲われる体験。子どもの頃の「小さな出来事」が、一生記憶に残る鮮烈さとなって浮きあがってきます。
●川上弘美『センセイの鞄』
ある時、思いがけずに居酒屋でばったり出会う中年女性と、元教師の交流がモチーフになっています。そのうちに日々の会食、散歩といった「小さなひとときの体験」が少しずつ積み重なって、温かな物語に育てあげられています。大事件ではなく、日常の一瞬の積み上げられた出来事が丁寧に扱われている愛着の深い作品です。

私の最近の作である『錯綜』は、定年退職後の再就職で人間関係に悩む元楽器製作者の独白小説です。結局は仕事をすべて辞め、続けていた株式投資で音楽を楽しみながら心豊かに生きていく前向きな思考を描いています。
観察力と感受性
物語に”息吹”を得る最大のポイントは「地味なディティール」と「心の揺れ」です。道端でふと見かけたおばあさんの手のシワ、友達がふと漏らした短いため息、カーテン越しに差し込む朝日――このような細部を日常的に観察し、「心が動く瞬間」をメモしておきましょう。
私自身、家族の何気ないしぐさや友人との沈黙の時間から、物語の重要なシーンにつなげてきました。また、「自然のにおい」、「音」、「目に映るもの」で想像が膨らんだときは、必ずスマートフォンのメモ機能で記録をしています。
日常で”何となく気になるもの”をストックする習慣が、いざ執筆するときに「描写」のとなって必ず活きます。さらに、他人や自分の心理的な葛藤・小さな違和感・好き嫌いのポイントなどに注目すると、より共感力のある登場人物を生み出せるでしょう。
👉例5:
●絲山秋子(いとやま あきこ)『沖で待つ』
繊細な人間関係に照らした生きづらい社会を、鋭い観察眼と感受性を最大限に活かして描いた短編集です。まだあまり広く知られていませんが、芥川賞受賞作です。
●津村記久子『ポトスライムの舟』
外見はサラリーマン小説のようですが、人間の内面に潜む強い感情の揺れを的確に捉えています。日常で表面化しにくい小さな違和感や生きづらさ、息苦しさを繊細に表現しているのがポイントです。
●高橋源一郎『さようなら、ギャングたち』
日常の言葉の表現のズレを巧みに使用して、「人間社会」を新たな角度で見直した作品。古典や大衆的な文化を織り交ぜ、新鮮な観察力に裏打ちされた感受性の強い断章形式の小説です。
オリジナルスタイルの確立
1.自分の思考性を見極める
あなたの”思考のクセ・こだわり・語感”が、そのまま作品の個性になります。論理型なら、伏線やプロット重視で読ませる構成を意識。直感型や感覚派なら、シーンや印象で心を動かす言葉を並べてよし!
「比喩」や「会話のテンポ」が気になった部分を意識的に何度も推敲するうちに、私は自分らしいリズムを見つけることができました。ワークシートとして、「好きな言葉」、「書いていて気持ちいい文体」、「参考したい作家」、「苦手な表現」などをリストアップしておき、都度見直すのもお勧めです。
また、新しいジャンルやテーマに挑戦するときは、憧れの作家・作品を “なぜそこに惹かれるのか”を深堀り・分析し、「自分の解釈」を盛り込むことで、自然な独創性が育っていきます。
👉例6:
●中上健次『岬』
「路地」と呼ばれる和歌山の被差別部落の舞台を、その土地の共同体と個人をめぐって”血縁”をテーマに、執着性と批判で描いています。まさに彼自身の思想そのものが小説の骨格となっている作品です。
●大江健三郎『個人的な体験』
自身の親族に障害があることを取り上げ、”尊厳と倫理” を戦後の日本において問い続けた作家です。『個人的な体験』は、作家自身の思想的・倫理的な苦悶の表情は表れています。
2.言葉の嗜好のこだわりを持つ
小説家にとって言葉は、画家の絵筆であり演奏家の音楽と同様です。言葉の響きとは文章に工夫を加えることでリズムが生まれ、どっしりとした長めの文を続ければ時間の重みが生まれます。また、短い文章の畳みかけでスピード感、緊張感が得られます。
これらの手法は多くの方が実践されていると思いますが、簡潔さを取るか、レトリックで美しい表現を心がけるかで個性を出すことができます。無駄を削ぎ落した明確な表現で読者を引き込み、鮮やか文章は色彩豊かに響きます。どちらも良さがありますから、自分にフィットした言葉の使い方を意識してみてください。
3.豊かな発想力と組み合わせの魅力
小説執筆の妙のひとつに”発想力”があります。独創的なアイデアはおもしろい小説になりますが、新しい発想だけではなく、実現的な要素を組み合わせる工夫などで新たな魅力も生まれるのです。
👉例7:
●「恋愛小説」と「歴史小説」を組み合わせる
●「日常」と「幻想」を掛け合わせる
組み合わせの発想は、その人の関心や価値観が自然に反映されることから、個性を作品に刻み込みやすい材料になります。
4. 継続力と粘り強さ
小説を書き続ける最大のコツは「自分に厳しい毎日」を作りあげることよりも、「小さな達成感」を積み重ねていくこと。
私は、本業で忙しい時期は“1日1文書くだけ”をルールにし、その一文でも必ず日記アプリに記録をして保存をしました。週末やスキマ時間には短いエピソードを膨らませるだけ。そのおかげで、「全部書かないとダメ」、「まとめて書かないとダメ」という考え方は捨てました。
また、書き上げたあとの推敲も「疲れたらその文章は寝かせて、時間をあけてから読み直す」、「とりあえず声に出してみる」といったマイルールを作れば、自分のペースで完成度が磨かれます。「量より続ける」、「完璧より一歩進める」を大切にすることで、粘り強さと作品の質の維持が両立できます。
5. 人間関係と社会との関わり
小説に不可欠なのが ”人間関係” のリアルな描写です。社交的な人も、出不精の人もそれぞれの関係性にしかない感情があります。わたしがこれまで関わったものを挙げれば、印象的な上司、客として関わった八百屋のおやじさん、SNSで見かけただけの誰かの悩みの相談文……。
こうした断片の人間観察の「実際のせりふや描写」をノートやスマートフォンにメモし、周囲の人間の“クセ・感情の揺れ”としてキャラクターの創造の材料にしました。
人と関わることに喜びを感じたら、対人トラブルの経験や失笑に終わった勘違いなどを盛り込み、逆に独りでいるのを好むのなら、「孤独・不安」をテーマにじっくり描いてみてください。どちらもあなたらしさに直結する作品が生まれることでしょう。「距離感」、「気まずさ」、「意外な一面」の小さな積み重ねに、深い物語を形づくる要素が見つかります。
6. 弱みを強みに変える視点
「弱点や失敗」も作家にとっては、印象的な個性につながる宝の山になります。「あがり症で人前でのプレゼンテーションで何度もしくじった」、「他人の気配りばかりし過ぎて疲れてしまった」など、これらの経験をわたしはそのまま主人公に使ったら、読者から「自分も同じ」と共感するメッセージをいただきました。
また、「飽きっぽい」、「理論的な構成を描くのが苦手」、「すぐに凹んでしまう」など、自分でマイナスに感じていた部分も、小説のキャラクターに反映させれば、想像を超えた魅力になります。
「他人と比べて自信がなくなった」、「考えすぎて前に進めない」といったあなたの ”弱さ” こそ、物語の根本を安定させる材料です。弱みを日常でメモし、「登場人物が背負うテーマ」として掘り下げ、徹底的に作品に活かしてください。

私は自分の気の弱さを上手く使って、『晩学作曲家のモノローグ』という作品を書きました。告白文の形式によるもので、自信のない控え目な語り口が良く似合い、自分の性格をさらけ出したような作品で、非常に愛着が湧いています。
ワーク企画
知識、経験を活かし、自分のスタイルを作るために、簡単にできるワークシートを用意しましたのでぜひ活用してください。各ステップの例はわたしの過去の体験を掲載しました。
1.自分発掘ワーク:簡単5ステップ
(ステップ1の例題の①から⑤はステップ2、3の例の同番号に連動しています。)
●ステップ1:人生で一番悩んだ・嬉しかった瞬間を思い出して書き出す
👉例:①学生時代に人間関係で悩んだ/②上司のひと言に振り回されて、自分の実務がまったくはかどらなかった/③うまい投資話をSNSで見つけたが、話に載ったところそれが詐欺だった/④海外旅行でその土地の文化の価値観に魅せられた/⑤仕事がうまくいって自分にご褒美を与えて美味しいものを食べたこと
●ステップ2:その瞬間、心のなかでどんなことを考えた?
👉例:①誰にも相談できずに苦しかった/②仕事上の立場の上下感に嫌気がさした/③うまい話はないので、慎重な行動を取らなければならないと感じた/④その土地に移住したくなった/⑤努力することで自分の成長や豊かさにつながる大切さに気付いた
●ステップ3:その体験は、今の自分の考え方にどう影響している?
👉例:①同じ悩みの人に親身になれる/②自由な生き方を求めるようになった/③自分で学び考え、発想する思考に切り替えた/④その土地の利点を活かした仕事をするようになった/⑤諦めない癖が身に付いた
●ステップ4:自分しか知らない、家族・友人のクセや言葉を10個挙げる。
👉例:家族間でしか通じないニッチな話題が存在する/「ありがとう」/「感謝します」/「すごいね」/「ほぼほぼ○○」/「すなわち……」/眼をパチクリさせる/鼻の穴をほじる/用もないのにスマホを見る/座ると必ず足を組む
●ステップ5:この中から「物語のネタになりそうなもの」に★をつける
👉例:
「★上司のひと言に振り回されて、自分の実務がまったくはかどらなかった」→「物語のひとコマ」に取り入れて、人の気持ちを汲む大切さを訴える」
「★うまい投資話をSNSで見つけたが、話に載ったところそれが詐欺だった」→「体験をもとにリアルな詐欺実話」を以降のステップを参照して組み立てる 👈読者の注意喚起としての役割を担うことになる
「★すごいね」、「★座ると必ず足を組む」→登場人物の口ぐせに採用
「★すなわち……」→タイトルに採用する 👈先を読みたくなる関心を抱かせる
このワークシートに、毎週1回取り組むことで、”自分だからこそ描ける体験”が増えていきます。
2.今日から使える執筆力アップTips
●Tips1:ネタ帳はスマホのメモでOK。”思い出したこと、街中で見た印象的な光景、感情が動いた瞬間”の3項目を必ず1行ずつ記録する。
👉例:
過去に同僚がまったく仕事をしないで、一日中おしゃべりばかりしていることを思い出した。
政治家の演説を眼にしたが、政策を訴えずに名前だけを述べてPRしていた。
心理学の名著を読んで、人の心の動きや性質が理解できた。
●Tips2:登場人物を設定する時は、”自分か家族の特徴・クセ”を一つ混ぜるとリアルさが出る。
👉例:
頭をすぐに掻く/声が大きい/極端に猫背/咳き込みやすい/汗を掻きやすい/歩く速度が平均より早い 等
●Tips3:せりふは実際に声に出して読むと、違和感をチェックできる。
自分で書いたせりふをいくつか声に出して読んでみると、しっくりくる・こないがよくわかります。
●Tips4:短編・エッセイでも構わないので、「一つの結末」まで書いてみることを目標にする。
繁忙などの理由で、途中で書き進めることができなく中断したものは、時間ができた段階で必ず最後まで書くことはとても大切なことです。途中まで書いた作品は、その後はいい作品に発展することがありますので、最後まで書くことをいつも念頭に置きましょう。
●Tips5:迷ったら、”好きな作家から得たヒント”、“自分ならどう行動するか” を混ぜてみると意外に執筆は進む。
👉例:次のようなスタンスを文章に入れてみる
自分の好きな作家の表現を深掘りしたものを、自分なりに表現し直す/言葉尻に「なのである」といった強調の特徴を見せる/理不尽なことが起きたら、必ず他人が是正する行動を入れる/険悪なムードに陥ったら、その場から離れるような設定/人との争いは避ける思考を一貫させる/それぞれの場面にちょっとした温かみを持たせる工夫 等
●Tips6:推敲する時は、”一日寝かせてからする”、“スマホ音声読み”がおすすめ。客観的に見ることでミスや違和感が減らせる。
時間を置いてから見直すと、深い次元でのミスの発見、より豊かな表現などの発想ができます。
3.ワークシート&チェックリスト
●すぐに使える!「自分の物語化発掘シート」
| 「自分の物語化」発掘ワークシート | ||
| 質問 | 記入例 | |
| 1 | 今日、一番印象に残ったことは? | 昼休みに同僚が放った一言で、少し悲しくなった。 |
| 2 | その時、どんな気持ちがわいた? | 理解されない寂しさ、つい嘘をついた後悔 |
| 3 | 過去に同じような感情を抱いたエピソードは? | 中学生の時にも同じ寂しさがあった。 |
| 4 | それを物語やキャラに転用すると? | 秘密を隠し続けていた主人公を ”涙を決して流さない設定” にした。 |
| 5 | 今日学んだこと・新たな発見 | 人は本当の本心をすぐに言えないことが多い。 |
些細な自分の気持ちを振り返って小説に活かしてみましょう。
●続けられた実感を得る!「執筆継続チェックリスト」
| 執筆継続チェックリスト | |
| □ | 毎日・週1回、1文でも何か書いた。 |
| □ | ネタ帳やメモアプリに、最低1つネタを書き溜めた。 |
| □ | 一度は書く気が起きなかったけれど、再開した日があった。 |
| □ | 完成せずとも、”途中まででok”と自分を許せた日があった。 |
| □ | この記事で取り組んだワークやTipsを1つは実践した。 |
3つ以上のチェックがつけば、続ける力があなたの武器になりつつあります。
●モチベが下がったら試してほしい「やる気復活ワーク」
| モチベーション維持ワーク |
| 過去に書いた自分の文章やメモを、”1か所”だけ褒めてみる。 |
| 憧れの作家や好きなYouTuberの作品を10分眺めて、「なぜ好きか」を言葉にして書き出す。 |
| SNSや友人に「今日は1文書けた」とだけ報告し、小さな ”いいね” をもらう。 |
| ストーリーの結末を妄想して、「こうなったらおもしろい!」と自由に落書きしてみる。 |
| 書けない日は「今日はネタ集めの日」と割り切って、外を歩いたり映画を観て刺激を得る。 |
●「書いた後」の発表・シェア入門ガイド
| 発表・シェア入門ガイド | |
| 1 | まずは家族や信頼できる友人1人に読んでもらう。 |
| 2 | note・ブログ・エッセイ投稿サイトで、「気軽な短編・エピソード」として載せてみる。 |
| 3 | X(旧Twitter)やinstagramに冒頭だけ、1文だけでも投稿してみる。ハッシュタグ付きもおすすめ。 |
| 4 | 初心者向け投稿SNS(note、NovelⅮaysなど)は「未完成」でも歓迎されやすい。 |
| 5 | 感想が来なければ「自分に○を付ける」気持ちで、反応を記録して次回の改善点にも活用する。 |
| 6 | 心が折れそうな時は、他の人の作品の「温かい感想欄」から元気を分けてもらう。 |
よくある悩み&その解決策Q&A
A:どんな日常でも、多くの人が共感できる”困った実話”や“小さな感情の揺れ”はあります。家族、友人との会話、自分の好きなもの、苦手な瞬間まで、全部書き出してみましょう。例えば、「通勤電車の混雑によるうんざり感」、「昔、親に言われて傷ついたひと言」も十分なストーリーネタです。
A:”自分の弱み・コンプレックス・苦手意識”を物語に入れましょう。他人が隠しがちな部分ほど、オリジナル性が高まります。自分の短所をキャラの性格や物語の中の葛藤として使うと、圧倒的な独自性が生れます。
A:”1日1文だけ”でもOKという自分のルールから始めましょう。週末だけでもまとめて書く、途中で飽きても「推敲だけはする」など、ハードルを下げれば自然と続けられます。少しの達成感を積み重ねることが重要です。
A:最初から完璧を目指さずに、「まずは家族や読者1人に感想をもらう」、「推敲して一部だけ公開する」から始めると安心です。自分の声、つまり作風を認めてくれる人を巻き込むことで、自信も自然に湧いてきます。
A:まったく心配することはありません。わたしも遅いほうで、少ないときは本当に1行しか書けない日もあります。それでも、自分のペースで毎日書き続けることが大切です。わずかな時間でも継続すれば、執筆力は確実に伸びます。努力はいつか必ず実を結びますので、焦らずに続けていきましょう。
A:物語の構成に迷ったときは、主人公に試練を与えてみましょう。「敵との戦いで完全に劣勢になり屈辱を受けた」、「入学試験でほとんど解けずに落ちた」、「職場の上司に”無能だからもういなくてもいい”と言われ世間が嫌になった」など、どんな内容でも構いません。
そこから他人の励ましや、運の向上を取り入れ復活するストーリーでもおもしろいのではないでしょうか。その過程で、自分にしか経験できなかったことを取り入れて組み立ててみてください。
まとめ
もしあなたが小説を書く自信を持てないなら、まずは「今日起きた些細な出来事」を一行だけでも書いてみましょう。わたしも初めは自信度ゼロからのスタートでしたが、敢えて失敗談を書いたりして、同業の方々は「ああ、こういうことは誰でも経験するね」と共感してくれています。
どんなジャンルでも、「自分だけの実体験×観察した感情」を組み合わせて、誰にも書けないオリジナル作品が生れます。ぜひあなたの「小さな体験」をネタに変えて、次の物語に活かしてみてください。
意識的に”生活の断片・小さな感情”を拾い集めて観察し、人間関係、弱点も上手に作品に投入すれば、誰にも書けない説得力・厚み・リアルさを持った作品づくりに取り組めます。
他人の手法に縛られず、「自分自身の経験」を物語の核として前向きに磨き続けること。小説の執筆作業そのものが、あなたの悩みや価値を最大限にする自己理解法である――そう信じて、今日から一行ずつ書き始めましょう。
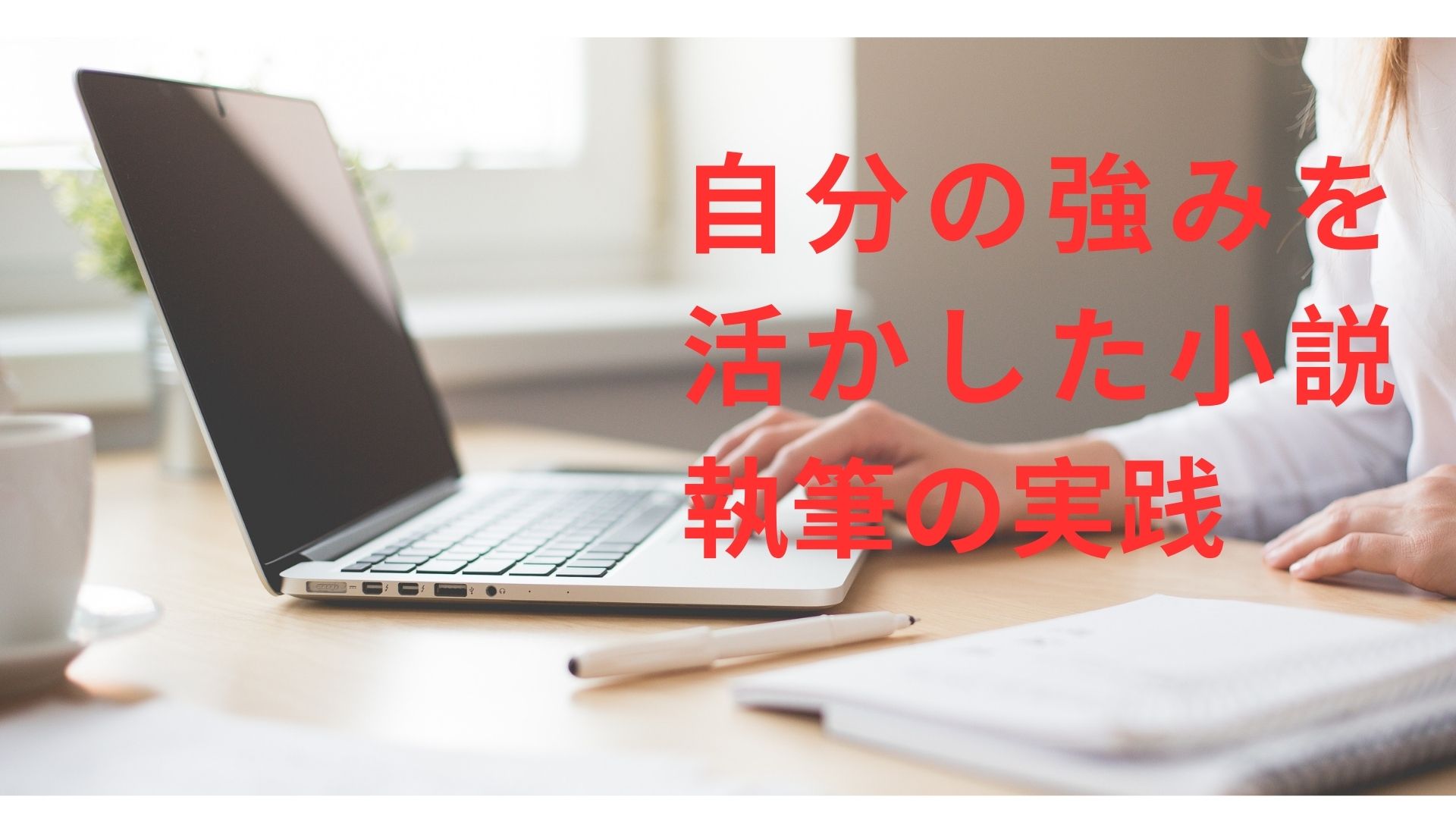


コメント