物語を書くときに、主軸となるプロットばかりに意識が集中しがちですが、読者の心に物語を「広げ」「深め」「残す」ためには、あえて主筋の外側に目を向けることが必要です。ここで注目したいのが「サイドストーリー(脇筋)」という構成技法になります。
脇筋は単なるおまけや背景ではありません。使い方次第で物語の重心をずらし、主筋を立体的に浮かび上がらせる力を備えています。この記事では、サイドストーリーの効果的な使い方を、項目ごとにご紹介します。
サイドストーリーは脇役の物語、主筋の引き立て役
まず、「サイドストーリー(脇筋)」とは何かを明確にしておきましょう。サイドストーリーとは、物語の主軸(メインプロット)とは別に展開される補助的な物語線を言います。しばしば脇役の視点や別の時間軸、または異なる出来事を通して語られ、主筋とは直接交わらないこともあります。
サイドストーリーは単なる「おまけ」や「寄り道」ではなく、以下のような役割を担います。
1 主人公や物語世界の理解を深める
2 作品のテーマやメッセージを別角度から照らす
3 感情の緩急を演出し、読者の集中力を持続させる
4 隠された背景や動機を補完し、物語に奥行きを持たせる
例えば、戦争小説で、前線の兵士たちの闘いが主筋だとすれば、その背後で家族が不安の中で暮らす日々や故郷の生活の変化を描く物語がサイドストーリーとなります。直接の展開に関与しなくても、読者の理解度や感情の深さを与えることに大きく貢献するのです。
サイドストーリーは「もうひとつの視点から描く物語のレンズ」であり、主筋を引き立てる「語られざる言葉」として機能します。
サイドストーリーを挿入する場合は、私は脇筋を主筋の一部に埋め込む構成を取ることが多いです。たとえば、地文とせりふで主筋が進んだ時に、その章の中で段落を変えて一つのブロックとして挿入するイメージです。
主筋に複雑に脇筋を文章単位で絡ませるとその後の展開がややこしくなり、読者も理解がしにくくなるのは必定です。できるだけ、シンプルに主筋と脇筋の関係を構成させていくことは重要な要素ですので、意識しておく必要があります。
サイドストーリーを活用した演出法6選
1. 主筋との「距離感」を演出する
サイドストーリーは、別の角度から挿入して、間接的にテーマやメッセージを読者の心に残すことができます。まず意識したいのは、主筋とどれだけ距離をとるかという点なります。
●距離が近ければ、主筋の補足や裏面を描くことになり、より厚みのある人物像や動機の補強につながる。
●距離が遠ければ、主筋とは独立した世界を持ちつつ、テーマや空気感で呼応し合う「鏡像構造」として機能する。
たとえば、主人公が復讐に燃える物語の裏で、かつて同じ境遇に立ちながらも赦しを選んだ人物の生涯を描くと、「復讐と赦し」というテーマが読者の中で二重に鳴り響くようになります。
サイドストーリーの一般的事例としては、次のものが挙げられるでしょう。
👉例:村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』
主人公・岡田が失踪した妻を探す物語(主筋)と並行して、戦争体験者や謎の人物の語る過去のエピソードが多数挿入されます。
一見無関係な脇筋に思えますが、登場人物の記憶や暴力の本質を通じて、岡田の旅と内的成長を照射しており、距離を取りながらも深く主筋とつながっています。
サイドストーリーは長編小説で使われる印象が強いですが、短編作品でも巧みに取り入れられることがあります。短編では限られた文字数の中で「主筋を際立たせる脇筋」がより精密に設計されていることがわかります。
👉例:梶井基次郎『檸檬』
表面的には主人公の心の不調と街をさまよう行動が主筋ですが、その背後にある「芸術への感受性」や「現実からの逃避」が、店の中での異様な描写や思考(サイドストーリー的な挿話)で遠くから照射されます。
主筋に寄り添いすぎず、遠くから間接的に心情を描く構造が特徴です。

日々執筆しているうちに、主筋に絡みつくエピソード、脇役の行動、主人公からの遠い視点の描写などを短編小説の構成の中に見い出すようになりました。アクセントとして淡々とした話の筋よりも緻密に配置し、しかもくどさのない物語の奥行き感を出せるようにすることがポイントになります。
2. 別視点で「沈黙の対話」を仕掛ける
『ものぐさがうぬぼれを救う』という作品を書いていたとき、主人公の親友について短いエピソードを加えようと思いつきました。この親友は主人公の生き方について直接意見を言うことはせず、ただ静かに見守るだけの人物です。親友が何も語らないことで、読者は「この人は何を考えていたのだろう」と想像するようになります。その結果、物語に深みが生まれたと感じました。
ここで大切なのは、
登場人物の心情や背景を説明しすぎないこと。
サイドストーリーは真実を詳しく説明するためではなく、「なぜこの人物はこうしたのか」と読者に考えさせる程度にとどめるほうが、読者が自分なりに物語を解釈できるようになります。このような書き方をすると、物語を読み終えた後にも余韻が残りやすくなります。
👉例:ジョン・ファウルズ『コレクター』
若い蝶の収集家が女性を監禁するという主筋のあとに、視点が切り替わり、監禁された女性の日記が脇筋として語られます。
同じ事件を真逆の立場から語ることで、読者の倫理的思考を揺さぶり、語られていない“ズレ”が強烈な緊張感を生み出しています。
👉例:芥川龍之介『藪の中』
登場人物ごとに同じ事件を語る多視点形式になっています。語られる内容に食い違いが生じることで、語られない“真実”への沈黙とも言うべきものが読者に委ねられています。
各証言が主筋にもなりうるのですが、それぞれが脇筋として機能し、全体が「語り合わない対話」になっている巧妙な構成がとてもユニークです。
3. 「影」を描いて主筋を対比させる
脇筋による「光」と「影」、「プラス」と「マイナス」などの対比で、物語の横幅が広がり、全体の深みも増します。
●主人公が成功をつかむ話であれば、その成功の陰で失われた友情や裏切られた者の視点を描く。
●革命を描く物語の裏で、それに巻き込まれた民衆の静かな絶望を綴る。
こうした「影の筋」は、物語のリアリティを高め、主筋に出てこない世界の重みを読者に知らせる役割を担います。単線ではなく、多層的なドラマが読者に共感を与えます。
『ものぐさがうぬぼれを救う』では、主人公が夢を実現する一方で、親友が最初から自分の夢をあきらめているというサイドストーリーを加えました。読者からは「主人公の成功の裏にある、親友の喪失感がリアルに伝わってきた」という感想をいただき、対比の力を強く感じました。自分自身の経験からも、物語を光と影の両面から描写することで、読者の心に深く残る作品になると実感しています。
👉例:チャールズ・ディケンズ『二都物語』
主人公ダーニーと彼を影のように追うカートンとの対比が、まさに「影の筋」です。
カートンは物語の中心ではありませんが、彼の存在があってこそ、主人公の選択や時代の運命が立体的に浮かび上がります。
特に最後の自己犠牲は、主筋を際立たせる象徴的な“裏”のドラマです。
👉例:太宰治『走れメロス』
表の筋はメロスの友情と信義の物語ですが、相手であるセリヌンティウスの静かな受難の時間が「影の物語」として描かれます。
出番は少ないものの、彼の存在がメロスの行動に深みと輝きを与え、主筋を力強く補完しています。
テクニックとして主筋と脇筋に現れる人物を対比させる際は、物語の性格によって微妙な投影の調整が必要だと感じています。
たとえば、先行き主人公と結びつく女性であれば、初めのうちはほんのりと遠くの幻影として配置させ、徐々に近づけていく手法を取ったり、対決姿勢にある人物であれば、強烈な印象を持たせておくなどの工夫をするようにしましょう。
4. テーマを「変奏」する
テーマを「変奏」すると、読者に一つのメッセージを異なる響きで届けることができる。
最近、「家族愛」をテーマにした小説で、主人公と疎遠になっている父親の過去をサイドストーリーとして描きました。結果は父親の若い頃に経験した失敗や後悔を描写することで、主人公が選んだ人生の重みがより強く伝わるようになりました。自分自身の経験からも、同じテーマを異なる視点から描き物語に深みが生まれ、主人公の人物像がより豊かに表現できると感じています。
👉例:伊坂幸太郎『グラスホッパー』
主筋では復讐を誓う男が主人公ですが、脇筋ではそれぞれ異なる事情を持つ殺し屋たちの人生が語られます。
全員が「人を殺す」という行為を共通項にしつつも、殺す理由も価値観もまるで異なり、「命」、「暴力」、「選択」といったテーマが変奏的に描かれています。
👉例:村田沙耶香『清潔な結婚』
結婚の常識に違和感を抱く主人公(主筋)と、彼女の過去の奇妙な友人との交流(脇筋)が重ねられます。
同じ「人間関係の形式性」というテーマを、違う角度から変奏することで、主人公の違和感がより際立って感じられます。

このような「変奏」を取り入れ、前述した「距離感」「多くを語らない」「影の対比」をうまく重ね合わせれば、より色彩豊かで奥行きのある作品が生まれます。独自の視点でさまざまな試みを実践してください。
5. テンポと感情の「緩急調整」に使う
サイドストーリーを使ってテンポや感情の緩急をコントロールすれば、物語に「呼吸」が生まれます。
初期の頃ですが、ある物語を淡々と書き進めていたときに少し変化をもたらせたかったわたしは、あるきっかけでこの手法を使ってみようと思い立ちました。サイドストーリーのテンポを主筋のとは違う快活なテンポの話題を取り入れてみると、その物語の雰囲気は一転して日が差した明るさを反映させることができたのです。
物語の方向性を変えたり、性格付けができる優れた手法であると思うようになり、今ではよく使うテクニックのひとつになっています。
また、私が最も効果を感じたのは、クライマックス直前に静かな脇筋を挟んだときです。激しい展開の合間に、主人公の幼少期の思い出を本筋に短く照射させただけなのですが、読者の感情がリセットされ、クライマックスの衝撃がより強く伝わったのです。執筆の現場で、緩急の重要性を身に沁みて実感しました。
●クライマックス前にあえて静かな脇筋を挿入し、主筋の劇性を引き立てる。
●激しい展開が続いた後に、穏やかなサイドストーリーで読者の心をクールダウンさせる。
これは映画の“間(ま)”や、音楽における“余韻”や“休符”に似た効果とも言えるでしょう。
主筋だけでは持続しにくい緊張は、サイドストーリーで変化させて調整する。
👉例:夏目漱石『こころ』
前半は先生と「私」の関係を描く静かな主筋ですが、後半では先生の過去(遺書)が突然語られ、物語のテンポと感情が一気に転調します。
一種の時系列をズラしたサイドストーリーとして機能しており、読者の感情を揺さぶる装置として秀逸です。
👉例:星新一『おーい でてこーい』
SF的なメイン展開(穴に物を捨てる社会の変化)に対し、ニュースや日常の描写が随所に挿入され、物語のスピードと読者の感情をコントロールしています。
遠く離れた脇筋のトーンが主筋を冷ややかに照らし、逆説的な緊張感が生まれます。
6. 独立性と統合性の両立を目指す
最後に大切なことは、サイドストーリーに「独立性」と「統合性」の両方を機能させることです。
●独立性:主筋から切り離しても成立する魅力や完成度を持つこと。
●統合性:最終的には主筋と共鳴し、読者の中で「全体の一部」として機能すること。
このバランスを保つことで、読者は「一つの世界の多面性」を感じ取り、物語全体に対する没入度が格段に上がります。
サイドストーリーに「独立性」を持たせて完成度を向上させ、かつ物語の歯車として主筋に対する「統合性」を強化させると、多様な側面からの輝きが増し、読者の関心は一層高まる。
短編小説で脇役のエピソードを独立した短い物語として書いたときのことです。最初は主筋と無関係のように見えても、最後に主人公と交差させたことで、読者から「全体が一つの世界としてバランスよくまとまっている」と良い反応をいただいたことがありました。自分の経験からも、サイドストーリーは「独立性」と「統合性」のバランスが大切なことを今も痛感しています。
👉例:東野圭吾『白夜行』
表向きは少年と少女の事件の真相を追うミステリーですが、物語の本筋は語られず、周囲の人々の人生を通して二人の姿が浮かび上がっていきます。
各章で描かれる“脇役たちの人生”は一つ一つが独立した物語として読めますが、すべてが主人公たちを暗示する影となっており、統合性も抜群です。
👉例:川上弘美『神様』
主筋は主人公とクマの散歩という不思議な日常描写ですが、クマとの会話から浮かび上がる過去の災害の記憶や社会の陰影が、独立した話として存在しつつ全体に静かな統一感をもたらします。
会話や風景が脇筋となって、言葉にされない「喪失」や「再生」の主題を読者に預けています。

サイドストーリーを機能的に活用できるテクニックが身につくと、書くことそのものが楽しくなります。アイデアに溢れた物語をワクワクする悦びを味わいながら、執筆活動を続けてください。
まとめ──主筋は道、サイドストーリーは風景
サイドストーリーという風景を添えることで、読者は立ち止まり、見回し、物語の真の意味を感じます。短編では「挿話」や「対話」、「風景描写」などに紛れ込むように描かれることが多く、読者がそれを“読み取る”楽しみが生まれるのです。限られた文量の中に重層構造を埋め込む手法は、まさに構成美の真骨頂です。
物語の展開を焦る必要はまったくありません。ときには寄り道や脇道こそが、物語の「真の記憶」となって残るものです。そう思って、あなたの物語にもそっと、もうひとつの灯火をともしてみてください。
私自身、サイドストーリーを意識し始めてから、小説を書くことがますます楽しくなりました。主筋だけでは描ききれない“余白”や“奥行”を脇筋が補ってくれるのです。これほど効果的なテクニックはぜひ活用したいと思いました。
もし今、物語に物足りなさを感じているなら、ぜひあなた自身の過去の経験、想いなどをサイドストーリーを使って加えてみてください。きっと、世界が変わる瞬間が訪れるはずです。
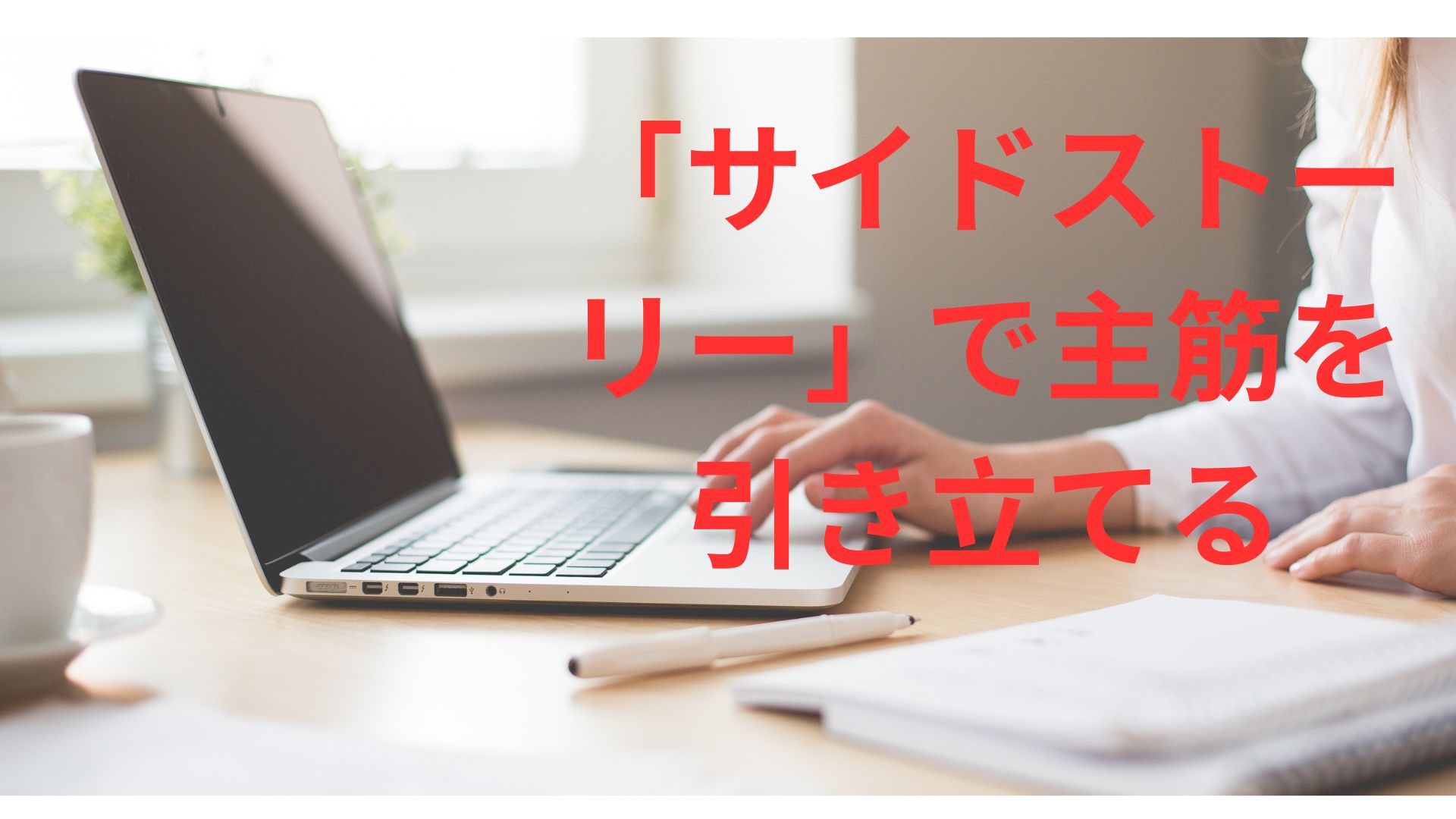


コメント