小説を書いていると、ふと「この先どう展開させればいいのか分からない」と立ち止まってしまう瞬間に遭遇することが必ず出てきます。「物語が動かない」、「キャラクターが迷走する」、あるいは「そもそもの構成がしっくりこない」。そんな創作上の「停滞」は、多くの書き手が経験するものです。
創作における“行き詰まり”は、単なる障害ではなく、視点を変えればアイデアの再出発点でもあります。この記事では、プロットづくりで迷ったときに見直したい観点や、思考を柔らかくするための具体的な工夫を7つに分けてご紹介します。
「最後まで書けない」主な原因とは?
まずは、なぜプロットを最後まで書けないのか、想定できる主な原因を挙げてみましょう。その原因を自分に当てはめて、把握してみることが大切です。
| 主な原因 | 説明 |
|---|---|
| モチベーションの低下 | 最初のアイデアに飽きてしまったり、納得のいく展開が編み出せない。日々の生活で優先順位が下がってしまったなど。 |
| ストーリーが迷走 | 曖昧な設定やキャラクターの動機が不明確で、話がどこに向かっているのかわからなくなる。 |
| 完璧主義 | 初稿から完璧にしようとして、前に進めなくなる。全体の物語の流れが見えなくなっている。 |
| 登場人物の動きが不自然 | キャラクターが著者の意志に反して勝手に動き、当初のプロット通りに進まない。 |
これらの対処として、私自身は「一旦机から離れ気分転換をする(出掛けるetc)」、「視点を変える」、「柔軟な発想をする」、「毎日少しでも時間をとってコツコツと執筆を進める」、「まずはストーリーの順番は考えずにプロットを書き切る」というような工夫をしながら執筆を進めるようにしています。
これらの自己管理をしていくうえで、最近はスランプや行き詰まるようなことが各段になくなりました。その方法は次の見出しでも解説をしていきます。
「迷い道」を抜け出す7つのヒント
プロットの作成で行き詰まりが生じたら、その原因に応じて次の7つ項目のいずれかを実践してみてください。
1.物語の“心臓部”を見つめ直す
プロットが絡まり始めたときは、まずストーリーの「本質」に立ち返ることが効果的です。
1 主人公の願望や目指したいゴールは何なのか?
2 その願いを阻む障害・壁はどこにあるか?
3 最終的に主人公はどんな変化を遂げるのか?
上記の3点が不明瞭な状態は、芯のない曖昧なストーリーになってしまうことが多くなります。自身にこのような問いかけをして、静かに考えてみましょう。テーマやキャラクターの動機が明確になると、物語全体の方向性も自然と浮かび上がってくるようになります。
私の場合は、プロットが迷走し始めてきたときは、必ず「この物語で主人公にどんな成長をさせたいのか?」の問いを自分に投げかけます。たとえば、以前書いた短編小説では、そうした自問で主人公が「自分の弱さを受け入れること」をゴールに設定し、“人間の弱さ”を押し出しました。その過程で、彼が直面する“親友との対立”、“失敗の連続”など、具体的な障害を物語に盛り込み、ストーリーに芯が生まれ納得のいく作品を誕生させました。
このような自分の体験から、プロットが行き詰ったときは「主人公の願い・障害・変化」の3点をセットにして紙に書き出し、次の展開を想像してひとつずつ掘り下げるようにしています。実際にしてみると物語に起伏が生じるとともに、全体の方向性がクリアになるのでお勧めです。
👉「物語の“心臓部”を見つめ直す」例:
●主人公が「過去に家族を失った苦しみを乗り越える」物語であれば、最終的に心を開ける相手との出会いが必要と考えてみる。
●「社会的な成功」を望む人物だったら、地位やお金では満たされない心の空虚さとの葛藤を描くのも一つの道です。
●逆に「変化を望まない主人公」が、環境の変化を強いられることでどう反応するか、というテーマも深掘りできます。

私の場合は、これらの事項に併せて、あとで解説する「キャラクターに試練を与える」ということをよくします。これはストーリー性の起伏も高め、読者の感情の波を高める効果があるということを、小説を書き始めの頃に学びました。
2.時系列を捨てて、自由に構造を組み替えてみる
創作の段階では、必ずしも「始まり→中盤→終わり」の順で構成を考える必要はありません。ときには、物語の山場やエンディングから逆算して組み立てることで、プロットに新たな発見が生まれこともあります。
ラストシーンから考えるみることで、「そこに至る過程に必要な出来事は何か?」という視点が生まれ、自然と流れが構築されていくことにつながることがあります。
👉「時系列を捨てて、自由に構造を組み替えてみる」例:
●ラストで「親子の再会」を描きたいのであれば、それが実現する背景にどんな誤解・葛藤・すれ違いが必要かを逆算してみる。
●物語の冒頭に“未来のワンシーン”を入れておいて、「この状況にどうやって至ったのか?」という興味で読者を引き込む構成もいつもとは違った展開を導けることがあります。
●断片的に「主人公が絶望の中で何かを叫ぶ場面」、「恋人が涙を流して去る場面」などを書き出してみると、その先のつなぎが見えてくる場合があります。
物語の構造を変えることは私自身もよく考えて実践しています。ラストシーンとして描くべきことを、冒頭に持ってきて、それに至る変遷を効果的に描く手法は読者を引き込むよい手段であることを学び、今では効果的な物語構成であることを認識しています。
3.キャラクターの“内面の声”に耳を傾けてみる
物語を動かす原動力となるのは、やはりキャラクターの感情や意志が大きく働くことが挙げられます。もしプロットが進まないと感じたら、彼らの内面にフォーカスしてみましょう。
作者自身がインタビュアーになったつもりで、次のような質問を投げかけてみると、自然な流れで登場人物たちの動きが見えてくるかもしれません。
私はプロットの創作で前に進まないときは、物語に登場させたそれぞれのキャラクターと次のような対話を重ね、キャラクター自身の意志のもとに、行動をつなげさせるような作業をしています。これによって、自主的な動きを見せることができるようなりました。
1「今、何に迷っている?」
2「誰のことが気がかり?」
3「これからどうしたい?」
この“対話”によって、キャラクターが生き生きと動き始めたとき、それは物語の停滞を打破する大きなヒントとなって、先の意外な展開に結びつくことになるものなのです。
👉「キャラクターの“内面の声”に耳を傾けてみる」例:
●キャラクターに日記を書かせてみる(「今日は最悪な一日だった。あいつの顔なんて二度と見たくない」など)。
●キャラ同士のLINEのやりとりや手紙文を試作してみると、意外な言葉遣いや関係性の機微が浮かび上がることがあります。
●「この人物が一番大切にしているものは何か?」を問いかけてみることで、プロット上の葛藤ポイントがクリアになってくることがあります。

実際にキャラクターと空想上で対話をしてみると、自分の頭の中で意外な回答が返ってくるなど、発想の転換にも役立ちますので、有効な方法だと思っています。
特に「何をしたいのか」の根本的な問いを投げかけると、そのあとの具体的な行動が順次導けたこともありましたので、度々そのような対話を頭の中で交わすことがあります。
4.あえて“制限”を設けてみる
自由度が高すぎると、逆に創作思考がぼやけてしまうことがあります。そんなときは、創作に小さなルールを設けてみるのがお勧めです。
1 ひとつの場面だけで完結させる
2 一つ章を会話文だけで展開する
3 キャラクターを二人に絞ってみる
ショートショートなどは場面の展開は少ないですし、会話文のみやキャラクターを極端に絞るような、あえて制限をつけることで創造力が刺激され、思いもよらない物語が生まれることもあります。
👉「あえて“制限”を設けてみる」例:
●「ある場面を電話越しの会話だけで進める」➡ 登場人物の感情や背景を、セリフと行間で描く力が試されます。
●「制限時間15分以内の出来事に限定する」➡ スピード感ある展開が必要になり、緊張感が出ます。
●「物語全体をひとつの喫茶店内だけで完結」➡ 人間関係のドラマや会話劇としての密度が増します。
自分の書き方のスタイルをあえて逸脱して書いてみるのも、新鮮で新たな知見が得られるものです。私も今までとまったく違ったスタイルの音楽家のインタビュー形式の小説を書いたときには、とても新しい価値観を持って取り組めました。たまに違った形式で書いてみることをぜひお勧めします。
5.プロットを“冷凍保存”してみる
どうしても筆が進まない場合は、思い切って一度物語から距離を置いてみるのも方法のひとつです。無理に考え続けるよりも数日間まったく別のことに集中して、再度見つめ直してみると思考がリフレッシュされることがあります。
しばらく時間を空けてから読み返すと、「この展開、今なら違う方法があるかもしれない」といった視点が自然と湧いてくることがあるものです。
実際に私が経験してきたことですが、どうしても物語が前に進まなくなったときは、思い切って一度パソコンを閉じます。そして、そして近所を散歩したり、別のことをするようにしています。以前、大きなスランプに突入したときは、2週間ほど執筆から離れ、料理作りに没頭したこともあります。すると、ある日突然、冷蔵庫の中にあった材料から新しいレシピを思いついたように、そのとき思案していた物語の突破口が開けお気に入りのアイデアがひらめいたのです。
この経験で「プロットをしばらく冷凍保存する」(しばらく寝かせてみる)ことは、大切であることを実感しています。無理に机に向かい続けるよりは、一度手放してみると、思いがけないアイデアが舞い降りてくることが多いものです。
👉「プロットを“冷凍保存”してみる」例:
●進まない作品から一旦離れて、しばらくは気分転換でまったく別なことをしたり、別のジャンル(詩、エッセイ、掌編など)に取り組んでみる。
●スマホのメモ帳にタイトルだけ残して、数日後に改めて開いてみると、よりしっくりくるタイトル思いつくことがあります。
●寝かせている間に読んだ他の作品や映画からも、無意識に新たな視点が生まれることも多いです。

前述のとおり、私はよく、ストーリーの進展が見られなかったり、無駄な時間ばかりが過ぎてしまうような場合は机から離れ、自分の趣味(散歩、投資)などに取り組みます。違うことに取り組んでいても、突如として素敵なアイデアが浮ぶことがよくあるものです。そんなときは、必ず忘れないようにメモをとっておくようにしています。
6.他者の視点を取り入れる勇気
行き詰まっているときこそ、誰かに話してみることが有効になったりもします。創作仲間や信頼できる友人にアイデアを話してみると、自分では気づけなかった発想をもらえたり、違った視点で反応が得られることがあります。
簡単な問いかけ――「このキャラ、魅力あると思う?」、「この展開どう感じる?」などでも、視野が大きく広がるきっかけになります。
私はこれまで、創作仲間をつくることに意味を感じ、相談相手としてその仲間にプロットの相談をしてきました。例えば、あるとき「主人公の動機が弱い」と自分では気づかなかった問題点を、その仲間がズバリ指摘してくれたことがありました。その一言がきっかけで物語全体を見直し、より深いテーマを盛り込むことができました。
出版を目的とする場合は出版社の編集者が的確なアドバイスをしてくれますが、そうでない場合で創作仲間をつくるには、小説創作などを目的にしたコミュニティなどに所属するとよいでしょう。今はSNSの“X”や“Facebook”などにさまざまなコミュニティが作られ、交流が活発になっていますので、それらに所属するのも一つの方法です。
また、家族に読書好きの方がいれば、読んでもらうのも率直なアドバイスをもらうことができます。私は書き終えたら家族にときどき目を通してもらっています。そのときに、「このキャラ、現実にいたらちょっと怖いかも……」と言われ、キャラクターの描写を柔らかく修正したこともあります。自分一人では見落としがちな視点を得ることができるので、ぜひ他者の意見を積極的に取り入れてみてください。
👉「他者の視点を取り入れる勇気」例:
●創作仲間との定期的なブレスト会(ブレインストーミング)などを開き、「この展開、どう感じる?」と聞いてみる。
●オンラインの創作コミュニティで「この設定、面白いと思いますか?」と意見を求める。
●家族や友人など、創作に詳しくない人に読んでもらい、「最初の数ページで惹きつけられるかどうか」の反応を聞いてみる。
7.キャラクターの前に「試練の石」を置いてみる
物語の進行が滞ってしまったとき、キャラクターの足元に「試練となる石ころ」をひとつ転がしてみるのも一つの手段です。順調すぎる展開ではキャラクターも読者も退屈してしまいます。あえて困難な状況を設定することで、人物の内面が揺れ動き、物語に波が生まれます。
この“試練”は、外的な事件でも、内面の葛藤でも構いません。大切なのは、キャラクター自身が「どう乗り越えるか」を模索し始めることを感情とらえて描写することです。
私がある長編を書いていたときのことでした。物語のストーリー性があまりに平坦なものになってしまったため、盛り上がりに欠けていると感じていました。ある時、主人公が信頼していた親友に裏切られるという“試練”を思い付き途中で加えてみたところ、主人公の葛藤や成長が一気に深まり、物語に厚みが生じました。
この経験は、プロットが停滞したときに「このキャラに今、どんな困難を与えたら面白くなるか?」という自問をさせるよいきっかけとなり、ひとつのコツをつかんだ感じがしています。実際にやってみると、キャラクターが自分の意志で動き出す瞬間に立ち会えることが多いと思います。
👉「キャラクターの前に“試練の石”を置いてみる」例:
●【心のブレーキ】誰かを愛することが怖くて、相手を突き放してしまう人物。けれどその人に救われる経験を通して、少しずつ心を開いていく。
●【状況の足枷】密室に閉じ込められる、地図を失う、頼りにしていた人物に裏切られる――。
物語の流れをガラリと変える「仕掛け」として有効です。
●【選択の板挟み】誰かを救うために、自分の信条を曲げなければならない。
その葛藤こそが、物語を深く人間らしいものにしていきます。
キャラクターの「動機」がはっきりしないときこそ、その人物に“わざと困らせる状況”を与えてみましょう。その反応の中に、物語を進める鍵が隠れているかもしれません。
対処法マップ(参考)
フローチャートと表を使って、行き詰まりの一部の対処のしかたについて、まとめてみました。状況によって参考として活用してみてください。
1.「プロット行き詰まり→対処法マップ」(フローチャート形式)
2.「制限の種類と創作への影響」(表形式)
前章で解説した、普段することはない「制限」を設けることは下の表のような効果が得られます。
このうち、私は主人公の困難を描く場面などでは、「時間の制限」を用いて緊迫感を出すことをしますし、「表現手段の制限」によって一人で語るモノローグで表現力に特色を見せることなどもよく採る手法です。
| 制限のタイプ | 例 | 得られる効果 |
|---|---|---|
| 時間の制限 | 1日以内の出来事 | テンポの良さ、緊迫感 |
| 場所の制限 | 舞台は教室のみ | 空間の密度、対話劇に集中できる |
| 登場人物の制限 | 2人だけ | 関係性の深堀りがしやすい |
| 表現手段の制限 | モノローグなし・会話のみ | 間接的な感情表現力の向上 |
まとめ:迷うことは、物語をより良くするための試行錯誤
1 物語の“心臓部”を見つめ直す
2 時系列を捨てて、自由に構造を組み替えてみる
3 キャラクターの“内面の声”に耳を傾けてみる
4 あえて「制限」を設けてみる
5 プロットを「冷凍保存」してみる(しばらく寝かせる)
6 他者の視点を取り入れてみる
7 キャラクターの前に「試練の石」を置いてみる
プロットで行き詰まるのは、作者が真剣に物語と向き合っている証でもあります。その迷いは、創作の質を高めるための“試練”となるのだと思います。
どんな作品も、最初から完璧に組み立てられるわけではありません。時には立ち止まり、時には振り返りながら完成されていくものです。迷った分だけ、あなたの作品には深みと味わいが増していくはずです。
私自身、何度もプロットで迷い、時には書くことに挫折してやめてしまいそうになったこともありました。でも、そうした“迷い道”を抜けた先で、思いがけないアイデアやキャラクターの行動による新しい一面に出会うことができました。今では、行き詰ることも創作の一部だと前向きに捉えています。あなたも、迷った分だけ物語に深みを見い出せると信じて、ぜひ自分だけのストーリーを紡いでみてください。
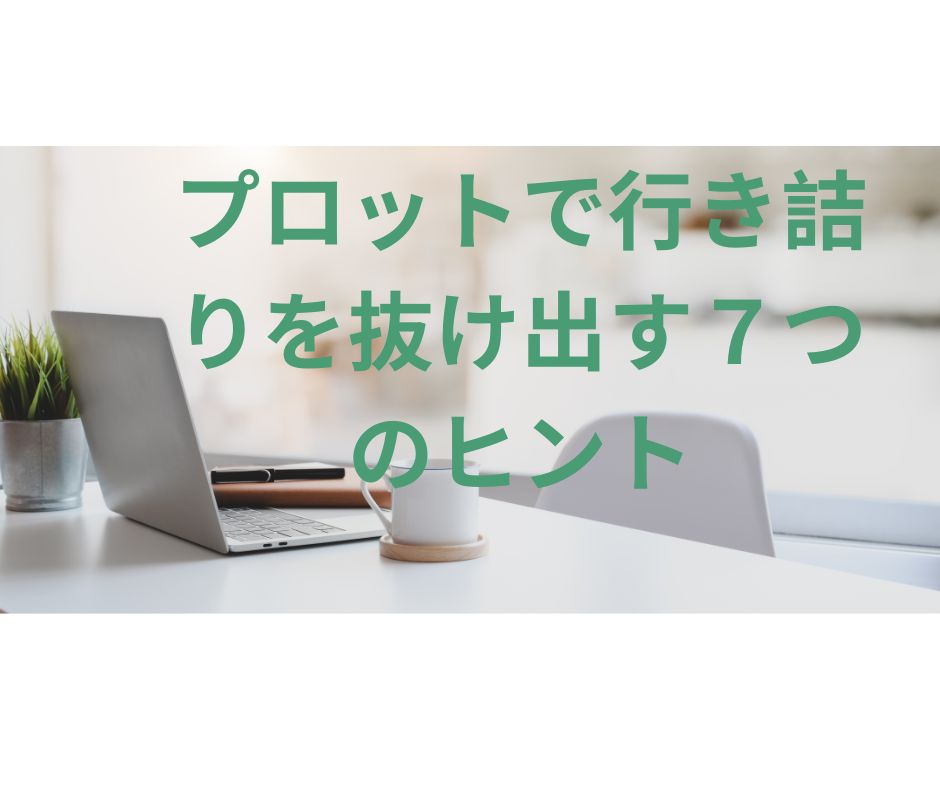


コメント