小説を書き始めた頃、私は「語り手」の地文と登場人物の「せりふ」を、それぞれ工夫をしているつもりでした。やがて、「両者の関係」にこそ難しさがあると気付き、再び悩むようになったのです。
読み手は、登場人物の言葉だけではなく、その文脈や背景からくる空気、異なる視点をどのように受け止めているのだろう?――書き手として、どうすれば両者が本当の意味で交じりあい、一つの舞台のように響き合うのかを長い間、探し続けてきました。
今回は自身の経験と、その中で生まれた発見をもとに、「語り」と「せりふ」の関係に焦点を当て、ジャンルごとの特徴を実践的に振り返ってみます。単なるコツや文章術の紹介ではなく、「本当に小説を書く現場で直面した悩み」を出発点にしました。少しでも執筆に悩む方の背中を押せれば幸いです。
「語り」と「せりふ」が交わる瞬間について
出来上がったある作品を友人に読んでもらったとき、「登場人物同士の会話は自然だけど、その間に挟まる地文が独立しているように見えてしまう」と言われた経験があります。その作品は「語り」と「せりふ」の一体感を持たせつつも、お互いが交差するなかで一定の関係性を持たせようとしたものでした。
はじめは「語り」と「せりふ」がきちんと混ざり合っていればと漠然と考えていましたが、実際には“響き合い”や“微妙なズレ”が、物語の余韻や深さを生むものだとあとから痛感しました。
私は「語り」と「せりふ」の関係を、ピアノ演奏に重ねて考えます。左手が右手を支えることもあれば、敢えてずらして印象的に響かせることもあるのです。読者を物語に引き込むためには、「統一感」だけでなく「未解決の余韻」も大切にしたい……これが私の小説観のひとつです。
重要なことは、
体験から学んだ「バランス」の難しさ
1.“融合への初体験”――意識しない「地文」と「せりふ」
2. 地文に“声”をにじませる効果
「せりふのような地文を書くこと」はキャラクターの癖、心情を語りのなかにこっそりと沁み込ませることです。例えば、ひとりの心配性の姉を描こうとする場合、
「姉は、きっと明日も明後日も、起き抜けに玄関の鍵の施錠を確かめるのだろう」
この地文自体が内心の“独り言”のように響き、せりふと地文のあいだ境界を自然と取り外してくれます。これにたどり着くまでに、何度か「あたかも説明しているようだ」と評される失敗を繰り返してきました。
小説を書くことは、「語りと「会話」中の“声”を調和よく文章に配置する作業です。地文には「語り手の視点」が必ず宿ります。三人称で語っても全知ではなく、より具体的に示された「焦点化された語り手」を選ぶと、語り手の温度がせりふと響き合うようになります。
上記の二つの特質を使い分けて表現するのですが、ズレの解釈を読者は、「地の文で感情を説明がないために、せりふだけでにじんだ感情を感じ取る」ようになります。
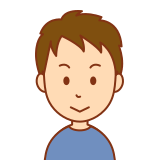
初めのうちはピンとこなくて当然だと思います。地文とせりふのそれぞれの性格を打ちだしつつ、両者の関係性を意識するところから始めてみましょう。書き続けていくうちに理解が深まり、そのあとの工夫につながっていくはずです。
3.“失敗”から生まれた発見~キャラクターの声が消える?
長編を書いていた時に、キャラクターの個性を出して“せりふ”を書いたつもりが、地文を挿入した瞬間に「誰が話しているのかわかりにくい」、「登場人物の声が消えかかっている」と家族から指摘を受けたことがありました。
この時、〈せりふと地文が対立し合い、せりふの個性が薄れてしまう〉状態であることに後から気が付きました。そこで対策として、
などの工夫を重ね、キャラクターの“声色”を地文にも反映できるように意識しています。
4.地文とせりふの“リレー”で臨場感豊かに
一部の作品では、「会話→心の声→行動描写→再び会話」とリレーのような形式を用いて、物語全体に独自のリズムと臨場感を出す工夫をしています。
👉例:
「やっぱり、まだ考えがまとまらないな……」
つぶやいた瞬間に、自分の心臓が一段と早く脈を打ったのを感じた。逃げ道を探している自分が、なんとも情けない。
「ごめん、ちょっとだけ時間くれる?」
この“心の声を地文とせりふに混在させる方法”は、最初、編集者に「ピンとこないし、わかりにくい」と言われていました。その後、何度も加筆修正をして、ようやく到達点に達したした苦い記憶が残っているのですが、同時にひとつの手法を身につけることができたと思っています。
後から自作を読み返すと、「読みにくい」と感じた場面がありました。軽快な会話が続いた直後に、長い地文を入れてしまったからです。
そこで自分なりに、前述のように「会話→地文→会話」の呼吸のリズムを意識し、一行の短い描写を差し挟んでテンポ感を出すようにしました。結果、読者の集中力を保てるようになり、特に物語の冒頭部分において、読者の読み進めるペースを設計しておくことの重要性を知ったのです。
地文とせりふの「リズムのよいリレー」を上手に設計して、読者の感情を誘えるように調整をしてみましょう。すなわち、
ことです。
読者は、言語より先に物語の性格でもある「構造のリズム」を感じ取って読んでいきます。波が不自然に崩れると、読者は無意識に「読みづらさ」を感じてしまうのです。とくに物語の“エンジン”を回す冒頭部分では、このリズムが読者をつなぎ止める重要な要素となります。
短編を書く時には、私は一貫して全体の構造を決めるようにしています。物語の構成が読者の読み進めるリズムを作ります。それが心地よさを醸し出すことになり、最後まで読んでもらえることにつながっています。
5.ジャンルで“使い分ける”――語尾と語調の実験
恋愛ものでは、地文で「……だろうか」、「……だった」というような柔らかめの語尾を多用していました。結果、無意識にせりふの“揺れる気持ち”と重なりやすくなったように実感しています。
一方、ミステリーやホラーで同じ調子を用いるのは、緩慢になって逆効果になります。ジャンルや場面ごとに大胆に語調を使い分けると、地文も“声”を持つようになるのだということがわかりました。
6.融合を阻む「リアリティ」の壁
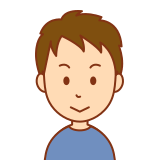
口論のシーンにおける融合の妙
登場人物同士が激しく言い合う シーンで地文とせりふを切り離すぎるのと、読者の熱量がさがりかねません。 一例として、
「ふざけるなよ!」
息が詰まる。言葉ばかりが先走り、息の鼓動は追いつかない。
「何を言うか? お前がわるいんだろ!」
怒鳴り声の間に、わざと詰まった感情の地文を差し挟み、会話の勢いと感情の動線がリンクするように私は仕上げました。結果、臨場感が伝わりやすくなったように思います。
7.融合の極意――“有効な独自ルールの発見”
いろいろと試行錯誤をして、最終的にわたしがたどり着いたのは、
地文もせりふも、「語り手」の世界観やリズムで響き合うように、
●シーンごとに地文とせりふの配分ルールを設定し、同じ“心の声”をせりふで地文でも繰り返してみる。
など、独自にルールや自作の縛りを決めて執筆するようにしています。一作ごとに「語り」と「声」が自然に重なり合う作品へと仕上がりやすくなりました。
ジャンル別の「語り」と「せりふ」の関係性
小説の各ジャンルには、それぞれ「地」と「声」の理想的な関係性を考えなければなりません。初めのうち、私は色々なジャンルを書いてきましたが、最終的には純文学のジャンルが自分にとってフィットするようになりました。以下に、今までの経験を通じて“構造的な視点”からそれぞれのジャンルにあった手法を解説します。
1. 恋愛小説:「言葉にできないを」をどう表すか
恋愛小説では会話ばかりを優先したばっかりに、なかなか登場人物の感情が深まらないという壁にぶつかりました。そこで、会話と会話の間に、「言葉にしきれない沈黙」や「しぐさ表情だけで伝わる緊張感」を表現する描写を丁寧にはさむようにした結果、読者から「感情の温度が伝わった」と言われたことは、今も執筆の大きな指針になっています。
恋愛小説の核は、「沈黙の中に潜む衝動」です。せりふを一歩引かせ、あえて語りすぎない地文を挟むことで、想いは深く読者に響きます。
たとえば「……うん。」「そっか。」という素っ気ないせりふのあとに、「彼女のまつげが震えていた」と入れるだけで、物語は厚みを持つようになります。
👉例:『ノルウェイの森』 村上春樹
「ねえ、キスしてもいい?」直子は言った。
「もちろんさ」と僕は答えた。
でも実際には僕たちはしばらくのあいだ黙って歩き続けた。
[解説]:せりふは率直で感情の表出がありつつも、地文が「言葉に出なかった真実」を静かに伝えています。沈黙や間が感情の濃度を上げる好例になります。
直子のせりふは、日常的でありながら深く、地文と地続きのように感じられます。沈黙や余韻を描く地文が、会話の感情の「漏れ」を静かに受け止めているのが特長です。
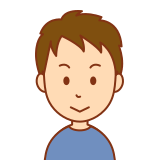
恋愛小説は、会話のなかで感情の盛り上がる噴出の受け皿になっているのが、地文である場合がすごく多いですね。対象的な静寂によって、作品が映えるのが効果的です。
2.ミステリー:「断片」と「編集」の関係
推理小説を書いた経験から感じたのは、せりふだけでは「謎」が解けてしまう危険があるということです。登場人物の会話はあくまで断片的にとどめ、本当の手がかりや意味づけは、地文で緻密に補う必要がありました。
一度、あえてすべてを会話で構成してみました。しかし、意外性が弱まり伏線の効果が得られず、サスペンスとしての魅力を出すには至らなかったのです。それ以来、「せりふはパズルのピース」、「地文はつなげる糸」と考えて全体を設計するようになりました。
ミステリーは物語の「真実」が構造上、常に後ろに隠されています。せりふはあくまで“断片”であり、そこに意味を与えるのが地文の「編集的機能」と言えるでしょう。読者が「気づかないように提示された情報」の接続を地文が担うことになるのです。
この関係性の調和が整うと、前半に張った伏線などは後半にうまく機能していくことになります。
👉例:『そして誰もいなくなった』 アガサ・クリスティ
「これで十人だな」ロジャーズが言った。
「部屋を案内します、こちらへ」
彼らはだまって従った。誰もまだ、互いに口を利こうとしなかった。
[解説]:せりふが最低限の情報しか語らず、地文が静かな不安を描写しますが、人物の心理には踏み込みません。この距離が読者に緊張感を残します。
そのため、せりふと地文の「分離」が戦略的に使われ、緊張と謎を保っています。淡々とした描写がかえって不安感を高め、読者は情報の取捨選択を迫られます。
恐怖感を表現する場合には、わたしならば単調な場面を淡々と描くようにし、先行きの不安感を募らせる効果を狙います。アガサ・クリスティーの事例にもあるように、人物のせりふは長々としては面白くなくなります。行動でソワソワさせたり、怯えさせる表現を入れていくようにしています。
3. ファンタジー:世界観と現実の「響き合い」
ファンタジーを書くうえでは、「地文」がその世界の歴史、神話、そして空気感を描き出し、「せりふ」は現在のキャラクターの目線や現実感を強調します。一度、世界観ばかりに気を取られて、「キャラクター」に命の宿りが見られない指摘を受けたことがありました。
それからは、地文で描かれる“おとぎ話の世界”と、キャラクター自身の“現実的な反応”、“ユーモア”を重ね合わせるように工夫をするようにしました。この二重性が世界の厚みや奥行きを生む要因となっていくものと感じています。
ファンタジーの世界では、両者が別の時間層を語ることが多くなります。むしろ“調和しないことが自然”という珍しいパターンが見られます。
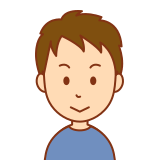
地文とせりふを別の次元、別の観点で書く場合には、人の意識のない深層心理に影響を与えるものと考えています。両者のあい対する視点が両極にあれば、読者の視野は広がり関心は深まるという認識で使ってみてください。
👉例:『ゲド戦記(影との戦い)』 アーシュラ・K・ル=グウィン
「本当の名前は、そのものの本質を表すのだ」
ゲドはそれを聞いて、ただうなずいた。
海と空の深さのような沈黙が、ふたりのあいだに降りた。
[解説]:地文は詩的で神話的、せりふは素朴で率直ながら含意が深いものがあります。言葉の背後に広がる世界を、地文が奥行きとして支えています。
地文は「神話的視点」、せりふは「今を生きる人間の声」として機能し、両者が調和よりもコントラストで響き合っています。静と動、古と新のバランスが世界を立ち上げています。
4.ホラー/サスペンス:断絶から生まれる「不穏」と「緊迫」
ホラーやサスペンスでは、“会話の無害さ”と“地文のさりげない異物感”のバランスが命だと、執筆を通じて感じています。一度、せりふだけで恐怖を描こうと試みましたが、友人から「意外に恐怖感はないね」と言われてしまった苦い思い出があります。
そこで、「登場人物の会話が続いた直後に、日常から微細にズレる違和感を地文ににじませる」手法を意識して、じわじわと恐怖が増していく構造が作れるようになりました。読み返してみると、その“断絶”こそが不安や緊迫感の原動力になっていたことに納得しました。
せりふが日常的であるほど、地文に差し込まれる微細な異常は際立ちます。調和ではなく「断絶」が恐怖を生む効果です。
地文に非日常性がうかがえれば、せりふとの結びつきも薄れたものになります。結果、せりふとの断絶によって、冷徹な効果が読者の恐怖的な心理を生むものと私は考えます。
👉例:『黒い家』 貴志祐介
「そんなに、保険って大事なんですか?」
渡部は笑顔を保ったまま頷いたが、手のひらにはうっすらと汗がにじんでいた。
[解説]:せりふは無害に聞こえますが、地文が不穏の兆しをわずかに差し込んでいます。このズレが読者に不気味さを植え付ける構造です。
5.ライトノベル/エンタメ:一体感の設計
日常会話に近い文章が多いライトノベルとエンタメですが、地文と会話文の境界をあえて曖昧にする書き方が有効だと気付きました。わたしも軽妙なテンポを意識して、地文でもキャラクターの口調や思考をダイレクトに描写することで、まるで会話の続きをそのまま読んでいるような感覚を出す工夫をしています。
一体感の演出は、物語のスピード感や親しみやすさに大きく左右するので、ジャンルによっては「語り」と「せりふ」の完全に溶け合わせてしまうのも一つの方法だと思います。
語り手と、ヒロインたちのせりふの交錯、つまり地文と会話の境界を感じさせない融合型の表現ということになります。
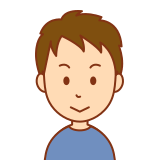
ライトノベル/エンタメが、地文とせりふの一体化が一番感じられるジャンルでしょう。融合などもあまり意識しなくても、自然に書けるのが特徴です。
👉例:『涼宮ハルヒの憂鬱』 谷川流
「あたし、宇宙人とか未来人とか超能力者に会ってみたいの!」
何を言ってるんだこの女は、と心の中でつぶやいた。
[解説]:語り手の内心=地文がすぐセリフの裏に“ツッコミ”として入るテンポのよさが持ち味です。まるで、ボケとツッコミの漫才のように一体化しています。
6.純文学:語りとせりふの曖昧で“にじみ合う”世界
純文学を一番多く書いてきたわたしの経験では、自分の内面や感情を「地文」と「せりふ」のどちらにも含め、あえて境目を目立たなくして書くことが多くなっています。“小説の書き方教室”の課題で提出した原稿で、「この部分は語り手のつぶやきなのか、人物自身の声なのか、読み手によって解釈の異なる作品」と評価されたことがありました。自分の書きたい“曖昧さ”が伝わったようで嬉しくなりました。
結局、読者が“自分で感じ取る”余白をいかに残せるかがこのジャンルの書き味だと体験的に実感したものでした。
内面のつぶやきがそのまませりふのように流れ込み、誰が語っているのかすら曖昧になることもあるのが純文学のおもしろさであり、大きな特徴となっています。
声の境界がぼやけることで、読者が“感情”から“気配”を読むようになります。
👉例:『金閣寺』 三島由紀夫
私はたしかにそれを「美しい」と感じた。しかしこの美しさには、私の存在の最も病的な部分が共鳴した。
[解説]:すべてが語りであり、同時に“心の声”のようでもあります。せりふすらも地文の文体に吸収されていて、語りと声の境がなくなっています。
上の『金閣寺』の例では、語り手の内面が極端に洗練された文体で語られていて、それがせりふをも飲み込んでしまうような印象を持ちました。せりふですら、地文のリズムや美学に取り込まれています。「声と語りの分離」がこの作品では意味をなさない世界を形成しています。境界をぼかすことで、読者は語りの中に沈んでいくことになるのです。
まとめ:物語の「奥行」は“語り”と“声”の間に生まれる
地文とせりふの関係性に悩み、さまざまな実践と失敗を重ねてきて今思うのは、「物語の奥行や温度感は両者の絶妙な距離と余白から生まれる」ということです。読者が「耳を澄ませて」主人公の内側や登場人物どうしの胸の内を感じ取れるよう、章の設計や構造を自分なりに工夫してきました。
各ジャンルによって変化する「語り」と「せりふ」の調和は、自分だけの経験や発見を重ねて得られるものです。そうした物語はより深く響きわたる作品に進化していくのだと信じています。
物語の深度と速度は、二つの“声”の調和で決まります。「地文」と「せりふ」は響き合った時、読者は文章の奥に「ひとつの生きた声」を聞き取るでしょう。あなた自身の工夫で「地文」と「せりふ」の性格を活かして、物語をうまく組み立ててみてください。



コメント