創作活動のなかで「比喩」はただの飾りではなく、文章に魂を宿す大切な表現方法の一つだと思います。かつては比喩を説明の助けとして使っていましたが、自らの試行錯誤で比喩が読む人の感覚を揺さぶり、想像の翼を広げる強力な道具であることに気づきました。
今では比喩がもたらす想像力の跳躍や読者の感覚を揺さぶる効果の大きさに驚いています。以下に、体験をもとにした比喩の使い方と発想力の伸ばし方をお伝えします。
比喩を効果的に使うための8つの「盲点と戦略」
1.比喩は「わかりやすさ」より「気づき」を与えるもの
初めのうちは説明として使っていた比喩ですが、使えば使うほど物足りなさを感じるとともに、比喩を使うことの深い意味があるのではないかと思うようになりました。そこで、比喩は読者に「ハッ」とさせる発見を届けると考え直し、深い想像の跳躍を促すように心掛けました。
「彼女の声は凍てついたガラスに爪を立てるような、センシティブな不快感をたたえていた」という風に想像力をかき立てる表現してみると、とで読んだ読者からもより鮮明なイメージが伝わっているという反応を実感しました。
本来、比喩は説明を省くためのものではありませんし、むしろ、読者に小さな驚きや発見を与えるためのものと解釈するべきでしょう。
比喩は「情報を増やす」道具というよりも、「連想を広げる」ための仕掛けである。
2.「似通った比喩」は避け、「微妙なズレ」を狙う
感覚の違う比喩を用いる例として、「怒りは火山の噴火」と単純にたとえるよりも、「怒りは抽斗の中でジワジワとこぼれ染みでるインクのよう」と少しズラした比喩の感覚はより深い印象を与え、違和感が読者の記憶に残るようになります。
また、違う例では、「夏のアスファルトが煮えたぎった釜のように熱い」という比喩を「夏のアスファルトは閉じたまぶたの裏で燃え尽きる花火のようにジリジリと続く」というように、少しひねりをくわえた表現も効果があります。
これは温度感のみならず、終わりの見えない焦燥感、倦怠感を感じさせることができます。比喩はぴったり似せるのではなく、少しだけズラして読者の想像力を刺激することが大切だとわたしは結論付けています。
比喩を考えるときは、「重なりあう」より「少しズラす」。
3.五感を交差させる比喩表現を試みる
視覚だけに頼らず、匂いや音、触感などの感覚の垣根を超えた比喩を積極的に取り入れてきました。たとえば、「彼の沈黙は凍った窓辺に溜まる白霜の冷たさのようだった」という表現は、多様な感覚を融合させた豊かな印象を与えました。レヴューでは「その冷たさが手に取るようにわかる」という反応をもらっています。
また、別の場面では、「ピアノの音が、青い柑橘の皮をむいた瞬間の香りのように広がった」と描写し、感覚の境界を超えた表現によって創作に新しい可能性をもたらしたものと思っています。
このように色を音で表現したり、匂いを形に置き換えたりする「共感覚的」比喩は一見突飛のようですが、読者の脳の中で異なる感覚が結びつき、強いイメージを呼び起こすきっかけをつくります。他にもいろいろと異なる感覚で置き換えは可能です。
👉例1:
●聴覚を視覚に置き換えた例:「彼女の沈黙は、黒板の端に残る白い粉のようにざらついていた」
●聴覚を味覚に変えた例:「その叫び声は、舌に残るレモンの渋みのように苦かった」
●匂いを時間に変えた例:「その部屋の香水は、時計の針を遅らせるように重たく漂っていた」
比喩を考える場合は、目に見えるものだけに頼らず、嗅覚や触覚、味覚まで動員してみる。
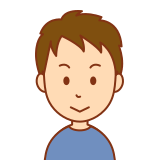
比喩は、一瞬「変だ」と思わせますが、読者の脳内で複数の感覚が結びつき、強い残像を残しますので、ぜひあなたの作品にも五感を使った比喩を取り入れてみてください。
4.比喩を登場人物の性格を映し出す鏡として使う
自作のキャラクターに合わせた比喩は、その人らしさを浮き彫りにします。少年は月を「半分かじったクッキー」に例え、詩人は「破れた銀紙」、科学者なら「重力に引かれながら静止した古い衛星」と描き分けることで、それぞれの人物の個性が際立ちました。
同様にロマンチストは雨を「閉じた傘の中で眠る小鳥の羽音」と表現し、冷めた老人であれば「錆びた蛇口の滴り」のようなど、人物の心情が比喩に現れてきます。
このように自作の登場人物は性格に合わせた比喩表現にし、読者にその人物の個性や感情をより伝わりやすくするようにしています。この技法はキャラクターの深みを増すうえで非常に効果的です。
比喩を考えるときは、「登場人物の性格に沿った比喩」を意識する。
比喩は単なる装飾ではなく、キャラクター造形そのものに直結しますし、語り手の心をそのまま写す「鏡」になります。
5. 独特な比喩はむしろ財産になる
私が「彼の笑顔は古い電気ポットのランプのようにぎこちなく光った」と風変りな比喩を使った時に戸惑いはありましたが、後になってその表現が不自然な温度感や苦しみを伝えていることに気づき、ボツにせずにそのまま使用しています。
創作の比喩は「不自然な表現」ほど本質が潜み、オリジナリティを秘めていると感じています。
「完璧な比喩」を目指すより、「どこか変だが気になる比喩」から独自のニュアンスが生まれる。
「おかしな比喩」を即座に捨ててしまうのは惜しいことです。少し考え直してみると、かえって小説の独自性につながるのではないかとわたしは思います。
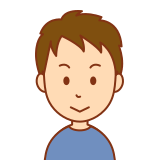
一度おかしな比喩だと感じたら、より身近な物に例え直すこともしてみてください。
また、「見た目に失敗かも……」という例からも、意外な意味合いが含まれているのを発見することができます。
👉例2:
●一見失敗:「彼女の歩き方は、修理中のエレベーターのようにぎこちなく上下していた」
→ 確かに不思議だが、「不安定」「機械的」「先が見えない」という情報を加えている。
こうした比喩は直さず残しておくと、後で作品にユニークさをもたらす財産になります。
6. 比喩は節度を持って散らすべき
比喩は多用しすぎると読者に負担をかけてしまいます。わたしは視覚表現ばかりを重ねた時に「文章が単調だ」と感じ、先述のとおり聴覚や触覚を織り交ぜることを意識しました。多様な感覚を散りばめることで一定のリズムが生まれ、深みが増しました。
過去に比喩を詰め込み過ぎた時、読者に疲れが出るのが見えてくるようでした。視覚・聴覚・触覚・嗅覚を織り交ぜ、まるで音楽の和声のように調和させる工夫を心がけています。
たとえば、「彼女の髪は光の川、笑顔は光の花、瞳は光の粒」という連続した視覚比喩を、視覚、聴覚、触覚を融合させ「彼女の髪は光の流れ、笑顔は昼下がりの果実の香り、瞳は冷たい鉱石の手触り感を秘めていた」という表現に変えた時は、読者の感情的な負担が減り、一層鮮明な印象を受けていただけました。比喩はリズムよく散らし、偏らせないことが肝心だと実感しています。
比喩の効果を出すコツは「偏らず散らす」こと。
比喩はひとつひとつが散っていても、頭のなかでつないでみて全体像が浮かび上がるように配置すると一層効果的です。
7. 言葉にしにくい感情を比喩で伝える
不安や孤独のうような説明が難しい心の動きは、比喩でこそ深く伝わります。「彼女の孤独は誰も乗らない止まった観覧車のゴンドラのように静寂に覆われていた」という言い回しはそうした効果を上げました。
描写中に試行錯誤を重ねたなかで、思考や感情の揺らぎを投影した「言葉で説明しにくい感覚」を、比喩が最も力を発揮することがわかりました。「彼は不安だった」という淡白な説明ではなく、「彼の不安は眠りかけに耳元でささやかれる正体の見えないざわめきのようだった」とするほうが、読者にその感情を追体験させやすくなります。
自身の創作で感情の微細な揺れを表現する際に、比喩ひとつで読者の心に触れる瞬間が訪れることを何度も経験しています。
単純な事実を比喩で補強する必要はありません。「速く走った」を「矢のように走った」と書いても、それほど効果はないのです。
説明不可能な心の揺らぎに比喩は力を発揮する。
比喩は「言葉の限界を突き破るための道具」です。言葉でそのまま表せるものに比喩はむしろ不要で、曖昧で捉えにくい心情に効くとされているのです。比喩は「言えないものを言わせる」魔法の道具になります。
8. 比喩は日常の発見から生まれるもの
比喩は頭で作り出すのではなく、見つけるものだと日頃から考えています。夜の街頭に集まる思いを馳せたり、バスの発車音を心臓の鼓動にたとえたりといった日々の観察眼がオリジナルな比喩をつくる原動力になっています。
ある時、駅のざわめきを耳にして「巨大な体内を流れる血の音のようだ」と思ったこともありました。こうした日常観察と感覚を研ぎ澄ませておくことがとても大切だと感じています。
比喩は、その人の感覚の「ズレ」や「発見」から生まれます。だからこそ誰にも真似できるものではありません。
小説家に必要なのは、
比喩を考える訓練を重ねるよりも、日常を観察する野心、自分の頭に思い浮かぶ連想を逃さず書き留める習慣を持つこと。
それが、唯一無二の比喩を生む土壌になると意識しています。
👉例3:日常の風景などから観察できる例
●夜のコンビニの照明を見て「眠らない水族館の水槽みたいだ」と感じる。
●冬の洗濯物を取り込んで「氷をまとった亡霊の衣のようだ」と思う。
●バスの発車ベルを聞いて「遠ざかる心臓の鼓動だ」と気づく。
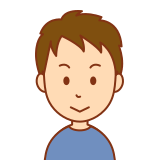
これらは頭で作ろうとしてもなかなか出てくるものではありません。ふとした瞬間の発見は忘れないうちにメモしておく心がけは、味わい深い比喩表現に一役買うことになるでしょう。
著名作家に見る「比喩」の妙技
実際に作家たちはどのような比喩を用いているのでしょうか。よく知られた作品からいくつか挙げてみましょう。
1. “比喩は「わかりやすさ」より「気づき」を与えるもの” の作品例
夏目漱石の『草枕』には有名な一節があります。
山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。
世情を直喩・暗喩的に捉えた構造から、主人公の「発見」として読者に投げかけています。角が立つ=摩擦が生じる、棹さす=流される、という使われた日常動作で抽象的な概念が鮮やかに提示されているのがわかると思います。
比喩は「イメージを膨らます」補助的な役割を持つのではありません。その情景・様態を「新しい見え方で見せる、発見させる」機能を有します。この作品はこの手法で、“知性・感情・意思”などの難しいテーマを主人公の実感に落とし込んで表現しています。
学べる点:直接的な内面の説明をするのではなく、外部の世界から比喩に導き心の揺らぎを可視化している。
漱石の比喩には、風景や自然を人間の心情に重ね、かつ照応させる力があります。たとえば「月は冷たい涙を流すように光っている」といった比喩では、自然現象が人間心理の延長として関わり、読者に「心情を風景に投影して読む」ことを気づかせます。
2. “「似かよった比喩」は避け、「微妙なズレ」を狙う” 作品例
芥川龍之介『羅生門』では、老婆の描写に次のような表現があります。
その頬の肉は、円い頬骨に沿うて、蜜柑の皮のようにたるんでいる。
「老婆の肌=しわくちゃ」というイメージ説明に終わることなく、想定もされない「蜜柑の皮」という対象を文章に落し、読者は思わず鮮烈な映像を呼び起こします。果物の皮を用いた「ズレた」比喩が、老婆の普通でない印象深さを引き立たせているのです。
月並みな「乾いたような頬」では心に残るようなことはありません。あえてズラして記憶に刺さる比喩になる好例です。
学べる点:対象物に対してズレた比喩は読者の印象を刺激する。
3. “五感を交差させる比喩表現を試みる” 作品例
川端康成は、感覚を交錯させて比喩を際立てることでは右に出る者はいいません。『雪国』の最も有名な冒頭もそのひとつです。
国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。
「夜の底が白い」という表現は、そのまま捉えれば辻褄が合っていません。視覚とここでは空間的な感覚を交錯させて、夜を「底」と称して読者に新しい感覚を届けています。
また『眠れる美女』には、
老人の胸をかすめるのは、冷たい花びらの匂いのようなものだった。
という比喩があり、嗅覚と触覚を重ねています。これが独特のミステリアスな予感を醸し出しているのです。共感覚的比喩は感覚の異世界へと誘い、「鮮明な事実」を読者に与えるのです。
学べる点:一つの感覚だけで描写せず、異なる感覚を交錯させることで、対象物の「気配」を感じさせている。
川端康成の比喩は、対象を単に飾るのではなく、五感を重ね合わせて存在を引き立てています。読者に直接「見せる」のではなく、そこに「想像している物をかたち作る」イメージを持たせる働きが生じています。
4. “比喩は「その人物らしさ」を映し出す鏡” の作品例
太宰治の比喩の特徴は、彼自身の経験してきた心理をそのまま人物像・語り手に重ねていることです。次に挙げる『人間失格』はそれがとても顕著です。
人間は、恋と革命のためなら、死ぬこともいとわぬ、ということを知りました。私には、それが、どうしても、信じられませんでした。
直接の比喩表現は見当たりませんが、彼の作品には「私は水に浮いた木の葉のようだ」、「私は紙人形のようだ」といった人物を自嘲的に扱う表現が頻繁に現れます。作家が同じ「無力感」を描くのでも、漱石なら哲学的に、芥川なら冷徹に、太宰なら自己卑下的にと、――比喩の選択手法にはその人格が影響するものなのです。
学べる点:自嘲的な比喩が著者の自己否定的で無力な思想を喚起させている。
キャラクターを描く場合でも、その人物の思想感を描くと「その人らしさ」が表現できます。
5. “独特な比喩はむしろ財産になる” の作品例
梶井基次郎の『檸檬』では、一見突飛な比喩が意外で独特の効果を出しています。
えたいの知れない不吉な塊が私の心を始終押えつけていた。
この「不吉な塊」という表現は、具体的な物に例えているとは言えません。そこに「見えてこない未知」がかえって心情をリアルに伝え、先の不安を醸しだしています。比喩を通じて「説明不能な心の圧迫感」がみごとに表現されていると言えます。
学べる点:説明が仕切れない著者の幻想的な心理が現実から離れた空想感を漂わせている。
比喩を「うまく言い表せない」状態にあるときが、私にも何度かありました。それはむしろ今では発見のチャンスだと考えています。この『檸檬』のように、「奇妙で未知な比喩」も作品の世界が広がっているのがわかります。この独自の作風が彼の人気作として、代表作にも位置づけられている所以だと思っています。
6.“比喩は節度を持って散らすべき” の作品例
谷崎潤一郎の『春琴抄』では、美の描写に比喩が多く使われて、それらは作品内で適度に散らされています。
春琴の声は、琴の音のようでもあり、また鶯の声のようでもあった。
ここで聴覚的比喩を重ねたあと、谷崎は別の場面でポツリと「春琴の姿を漆塗りの器」に例え、視覚的・触覚的な比喩を織り交ぜています。偏らせずに散らす比喩は、読者に負担をかけず、全体としてしつこすぎずに豊かな印象が保たれるように設計されています。
学べる点:対象を「美しい」と言わずに触感や音感を喚起させて、身体で感じられる比喩を使う。
谷崎の作品には、人間の身体や感覚を極端に誇張した比喩が多く見られます。『痴人の愛』などでは、女性の仕草や衣服を「絹のように音を立てる」、「蛇のようにくねる」といった比喩で、視覚だけでなく官能的な触覚や聴覚を読者に植えつけます。谷崎にとって比喩は、読者が「肉体を媒介にした感覚体験」を呼び起こす麻酔薬ように機能しています。
7. “言葉にしにくい感情を比喩で伝える” の作品例
芥川龍之介の『地獄変』では、絵師良秀の狂気を描いています。
その顔は、燃え上がる炎を前にした時の猿のようであった。
単に「狂気じみていた」と直接の説明を避け、炎と猿という異質なイメージを融合させることで、もはや手に負えないほどの恐ろしさを描き切っています。
学べる点:二つの異質なものの組み合わせで狂気性が表現され、ただならない様子が創出されている。
言葉で直接説明できないもの――恐怖、狂気、陶酔、虚無――に比喩は最も効力を発揮するものだと思っています。
8. “比喩を「作る」のではなく「見つける」”の作品例
村上春樹の文章には、日常の光景の中でふと見つかるような比喩が多くあります。
彼女の声は、午後のプールに浮かぶビーチボールのように軽かった。
特別に風変りなものではありませんが、日常の中から拾い出した比喩が彼の作風を支えています。
比喩は「頭で作る」よりも「日常の中で見つける」と前述しました。有名作家もまた、自分の感覚に忠実であったからこそ、独自の比喩を見つけ出す機会を常に探しているのだと思います。
学べる点:日常で目に留まる特異な様相から察知して、「日常と意外性の融合」が生まれている。
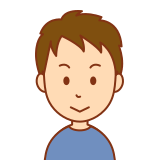
比喩は机に向かってひねり出すより、日常生活をよく観察して見つけてみてください。
まとめ
1.比喩を効果的に使うために
比喩は単なる装飾ではなく、創作の根幹を支える表現技術であると私は考えています。読者の感覚を揺さぶるためには、単に「似ている」比喩を使用するのではなく、少しズレた独自の視点を採用し、五感を融合させてみることが重要です。さらに、自作のキャラクターや感情を映し出す鏡として比喩を活用し、失敗と感じる表現も「宝の山」と捉えて加工し直す柔軟性が必要です。
比喩はリズムよく文章に散りばめ、日常の感覚から発見する習慣を持つことで、唯一無二の表現世界を築くことができます。こうして磨かれた比喩は、読者にとってあらたなふ風景や感情の宇宙を体験させる力強いツールとなります。
2.著名作家の比喩から学ぶ
漱石の発見的な比喩、芥川のずれた比喩、川端の共感覚的比喩、太宰の自嘲的比喩、梶井の未知の比喩、谷崎の散らし方、芥川の狂気の比喩、村上の生活感のある比喩――。
作家ごとに手法は違いますが、共通しているのは「比喩は世界を変えて見せる」こと。比喩とは、作家の文体や思想そのものを支える仕組みです。
小説家を志す方なら、比喩を飾りではなく「異化」の装置としてとらえ、自分だけの視点を探してください。それが、あなたの作品を唯一無二のものにしていくはずです。



コメント